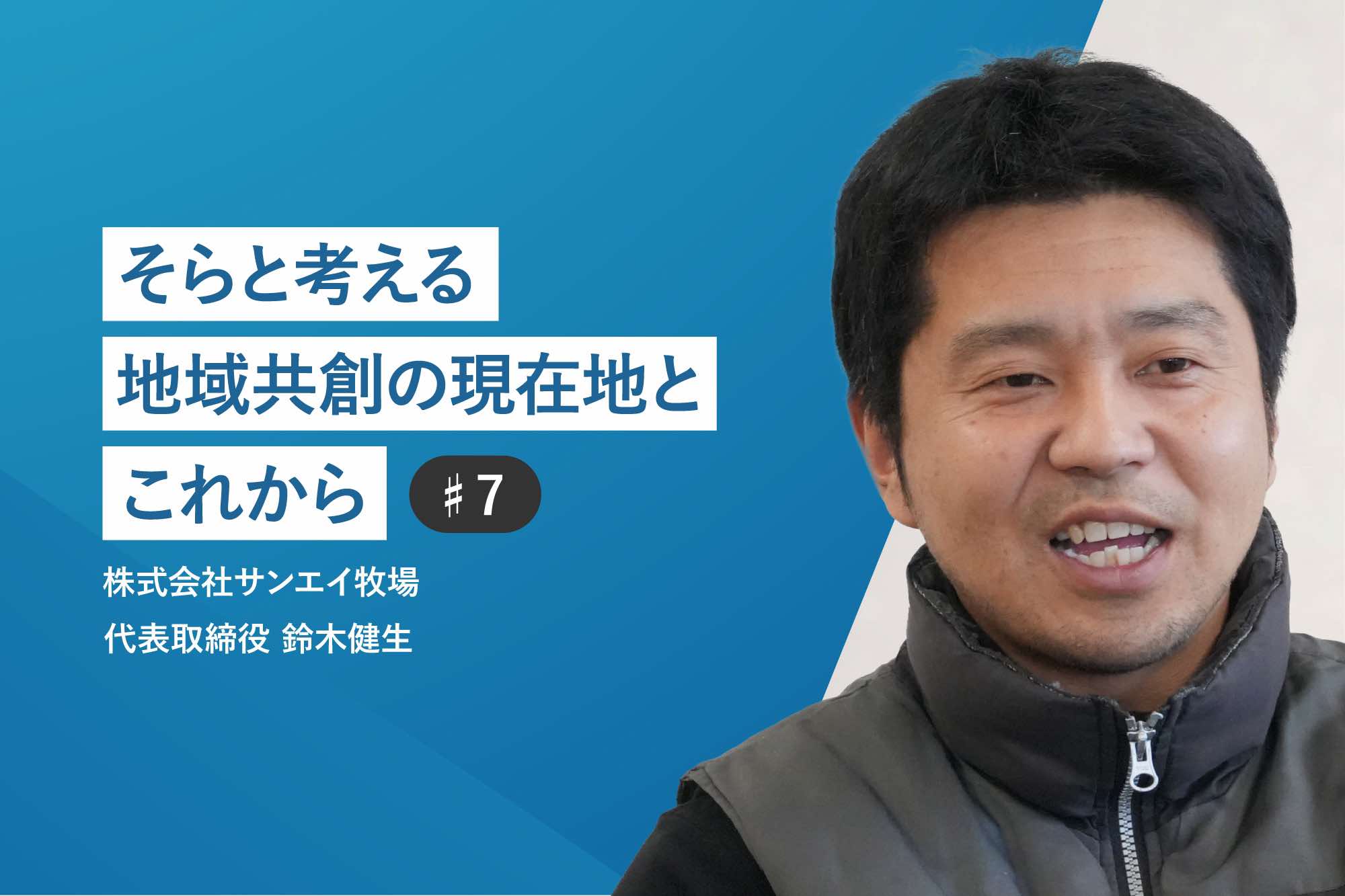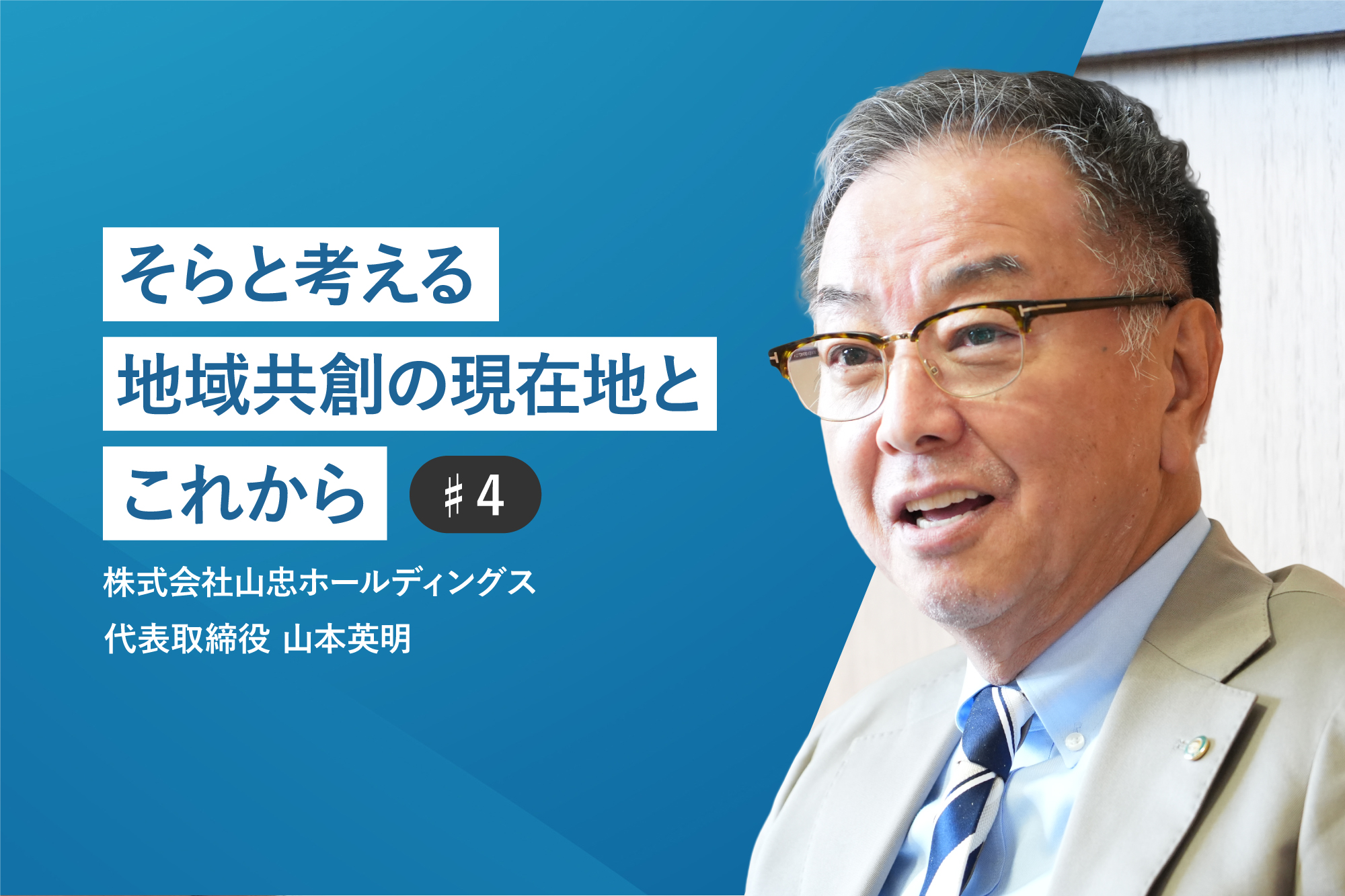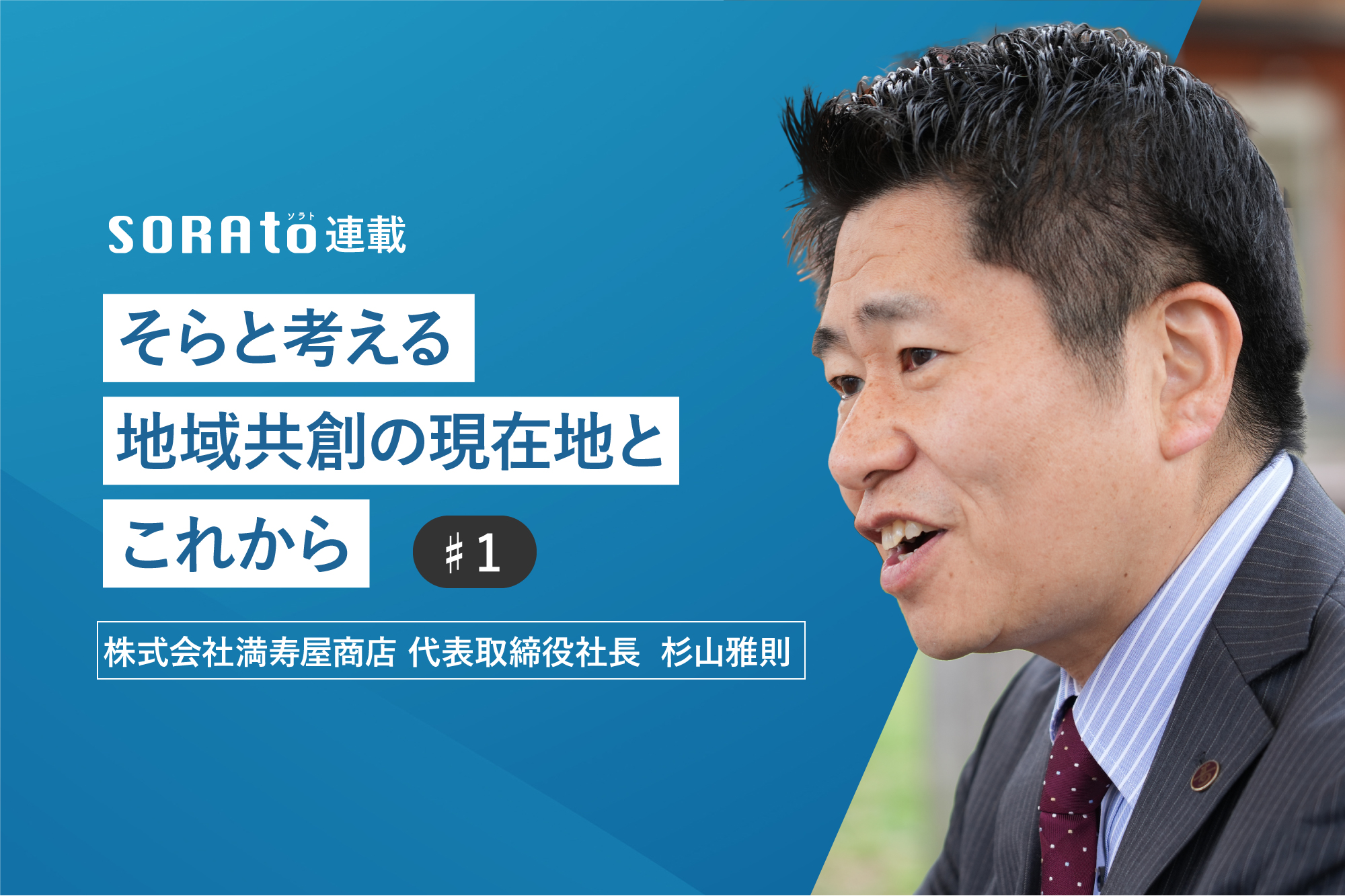第七回目のフロントランナーは、十勝を拠点とする電気工事会社「相互電業」。地域の電気インフラを支えるだけでなく、海外での電気工事事業の展開も視野に入れる同社は、いったいどのようなビジョンを描き、どのように前進しているのでしょうか。今回は、同社の社長として若くしてバトンを受け継ぎ、事業拡大とグループ形成を進めてきた板倉利幸氏に、幼少期のエピソードから留学体験、そして地域への想いまで、幅広く伺いました。(取材:株式会社そら 三浦豪 加藤直樹 / 記事・写真:スマヒロ編集部)
PROFILE
1979年、帯広市生まれ。帯広東小学校、帯広第六中学校(現・翔陽中学校)、帯広柏葉高校を経て、日本大学工学部卒。米国・サンディエゴの私立大学付属語学学校へ約2年間留学。2004年に相互電業に入社し、帯広市図書館改築工事に携わる。07年に一度退社し、日本創造教育研究所(大阪)にて経営研修を学んだ後、東京で営業を経験。09年に常務として再入社し、11年から副社長。2016年、35歳で代表取締役社長に就任。現在は国内外における電気工事事業の拡大だけでなく、人材育成にも注力し、十勝と世界をつなぐ新たな取り組みに挑戦している。
幼少期から受け継がれた“3代目”としての使命感

まずは板倉社長の幼少期についてお聞かせください。ご実家では創業者であるお祖父様の時代から続く会社だったと伺いましたが、どのように育ってこられたのでしょう?

私は1979年に帯広で生まれました。もともと父の男兄弟が3人いましたが、男の子が生まれず家系をどうするか、という話があったようです。そんな中で私が生まれ、「板倉家の3代目だな」と周囲から言われ続けてきました。幼い頃から祖父や父が経営する会社を「継ぐんだ」という刷り込みがあり、高校生の頃には「将来は会社を継ぎたい」と父に伝えていたくらいです。じいちゃん子でしたし、自分自身も「いつかは自分が」と思っていたんですね。

経営者になることに迷いはなかったですか?

全然なかったですね。ただ、子どもの頃は「電気工事会社が何をする会社か」まではピンときていなかったんです。北電さんのように電柱を建てる仕事をしているんだな、という程度でした(笑)。でも家業=将来はそこに入るのが当たり前、という感覚はずっと持っていました。
大学・留学時代に感じた異文化と“日本人”というアイデンティティ


高校卒業後は日本大学工学部に進まれ、その後はアメリカへ留学されたとのことですが、どのような学生生活を送られたのですか?

高校時代から理系だったので、大学は福島の郡山市にある日本大学工学部へ進学しました。4年間の大学生活は、友人と楽しく過ごしたり、自由に過ごしていましたね。卒業後にアメリカ・サンディエゴへ留学したのは、姉たちの影響も大きかったです。姉がヨーロッパに留学していたこともあり、「自分も海外を見てみたい」と。場所を選んだ理由は単純で「どうせなら暖かいところがいい」と(笑)。

実際にサンディエゴで2年間過ごしてみていかがでしたか?

ものすごく衝撃的でした。人種差別を目の当たりにして、初めて「日本人とは何か」「自分はアジア人なんだ」と強く意識させられましたね。アジア人同士が自然と集まることが多かったり、黒人の友人がレストランで差別的な扱いを受けていたり……。日本にいては想像しづらい経験でしたが、世界の多様性と同時に、社会の不平等を知る大きなきっかけになりました。

日本に戻られた後、すぐに相互電業へ入社されたのですか?

はい、2004年に入社し、帯広市図書館の新設現場で2年間ほど電気設備工事に携わりました。でもその後、一度会社を退職して経営研修の道へ進むんです。
経営研修で得た人材育成の視点──「会社は人生道場」


経営研修の道に進んだきっかけは何だったのでしょうか?

日本創造教育研究所の「起業家養成プログラム」を受講していたのが始まりです。二代目・三代目経営者が多く集まる研修で経営のノウハウや考え方を学び、一年かけてプログラムを修了しました。その後、「もっと実地でやってみろ」と社長(日本創造教育研究所)に言われ、大阪・東京を拠点にする研修会社で2年間、法人向けの営業を経験しました。

その2年間はどんな時間だったのでしょう?

平日は営業で企業を訪問し、土日は研修運営でほとんど休みなしでした。今では考えられない働き方ですが(笑)、さまざまな社長に直接会えたことは大きな財産です。社員を幸せにすることを真剣に考えている社長もいれば、私利私欲に走る方もいて、それによって会社の業績や雰囲気が大きく異なるのだと学びました。経営者の人間性が会社を支えるんだ、と痛感する場面も多かったですね。

今の相互電業での人材育成にも、そうした経験が活かされているのですね。

はい。人材育成の重要性はずっと意識しています。うちの父がよく「会社は人生道場だ」と言うんですよ。仕事を通じ、人として成長してほしいという思いが私自身にも根付いていて、新入社員を専門学校に通わせたり、研修制度を整えたり、実践の場をつくることに力を入れています。
若き社長就任と業界のしがらみ──“変革”への10年


2016年、35歳で社長に就任されたわけですが、その当時を振り返るとどのような苦労がありましたか?

副社長をやっていた時期に「早くバトンを渡してほしい」と父には何度も言っていたんです。でも、いざ社長になってみると見える景色が全然違う(笑)。業界内の政治的なつながりや、父が長く築いてきた人間関係に対して、私自身には実績も信用もなかったので、社長交代後すぐは苦戦しました。

古参の社員やお得意様との関係など、乗り越えるべきハードルが多かったんですね。

そうですね。10年ほど前に戻ってきたときは、新卒採用をまったくしていなかったので組織の高齢化も進んでいました。そこを思い切って若手採用を進めて今は平均年齢が30代まで下がったんです。技術力を蓄積するには10年単位でかかりますが、若い人材の活力は組織を変える原動力になります。ここは投資だと腹をくくってやっていますね。
地域インフラを守る使命──電気保安業務とグループ形成


事業内容としては、電気工事や施工管理だけでなく、電気保安業務も担っていると伺いました。地域を支えるうえで重要なポジションですね。

そうなんです。2016年に制度が変わり、北海道電気保安協会だけでなく民間でも保安業務が担えるようになりました。当社には電気主任技術者も在籍しているので、工事だけでなく保安点検をセットで請け負える。建物や施設の安全を守ることで、地域社会が安心して暮らせるようサポートするのも、私たちの大きな使命だと思っています。

地域の企業である相互電業が保安業務まで担ってくれるのは心強いですね。

さらに、後継者がいない電気工事会社をM&Aで引き継ぐ動きも進めています。地域にとって電気インフラはなくてはならないもの。だからこそ、その会社がなくなるとそこの町は困ってしまう。私たちが引き継ぐことで雇用や工事体制を守り、地域のインフラを維持していきたいんです。
外国人材×海外展開──「ミャンマーのためにもなる会社を」


若手不足が深刻化する中で、外国人材の採用や海外事業にも力を入れているそうですね。

はい。日本の電気工事業界は国家資格や高度な技術を要するため、簡単に外国人を採用できません。しかしながら、地元・十勝の工業高校の生徒数も年々減っているのが現状です。そこで私は、ミャンマーに注目しました。現地の日本語学校などとも連携し、ミャンマー人を採用して本格的に技術を身につけてもらう仕組みをつくりたいんです。

ミャンマーで電気工事会社を立ち上げる構想もお持ちとお聞きしました。

はい。日本の技術や安全管理をミャンマーに根付かせることができれば、現地の発展にも大きく寄与できるはずです。さらに将来的には、そのミャンマーの会社が日本の電気工事会社へ人材を派遣する仕組みを整えれば、日本側にとっても貴重な人材源になります。お互いがウィンウィンの関係を築けるんじゃないかな、と。

日本の高い技術を海外にも広げることで、十勝のみならず国際社会にも貢献するというわけですね。

そうですね。ミャンマーの方々はとても親日的で、笑顔が多い印象があります。日本のように安全管理や品質管理を徹底することで、きっと現地でも大きく活かせるのではないかと思います。
十勝への愛着と“フロンティア精神”──地域を守り、世界に打って出る


最後に、十勝という地域がさらに盛り上がるために必要なことは何だとお考えですか?

十勝の人たちには、フロンティア精神があると思うんです。広大な大地や厳しい自然環境の中で試行錯誤を続けてきた風土が、チャレンジを後押ししてくれる。私自身、留学や経営研修を経て感じたのは、「日本の経営理念や技術は世界に通用する」ということ。だからこそ、ただ地元に留まるだけでなく、世界にも打って出てほしいと考えています。

地域を守るだけではなく、外にも積極的につながりを求めるということですね。

ええ。海外とのつながりが生まれれば、逆に十勝という地域も外から見たときに魅力的に映ります。自然の豊かさ、食や観光資源の多様さ、そして人の温かさ──ここほど住みやすい場所はないですから。電気工事というインフラ整備の面からも、私たち相互電業が一翼を担っていきたいですね。

本日は貴重なお話をありがとうございました。板倉社長が描く未来の相互電業、そして十勝の発展が今後どのように結実していくのか、とても楽しみです。
PROFILE
加藤 直樹 | かとう なおき
群馬県前橋市出身。武蔵大学を卒業後、野村證券入社。最初の配属地、とかち帯広営業所でそら代表の米田健史と出会う。その後、大阪の支店で2年勤務。2024年2月、株式会社そらにジョイン。現在は社長室長として社長をサポートする。
PROFILE
三浦 豪 | みうら ごう
株式会社dandan 代表取締役 | PwCの戦略コンサルティングチームStrategy&、ベンチャーキャピタルの Reapraグループを経て、2021年に株式会社dandanを創業。人や組織は「だんだん」変容するというコンセプトで、企業研修や経営支援、コンサルティングを行っている。2023年に帯広市に移住したことをきっかけに、SORAtoインタビュー企画のディレクターとしても活動している。

今回の主役は、北海道・十勝に移住した三浦豪さん。米国シアトルのワシントン大学を卒業し、世界最大級のプロフェッショナルサービスファーム「プライスウォーターハウスクーパース(PwC)」の戦略コンサルティング...
過去の記事