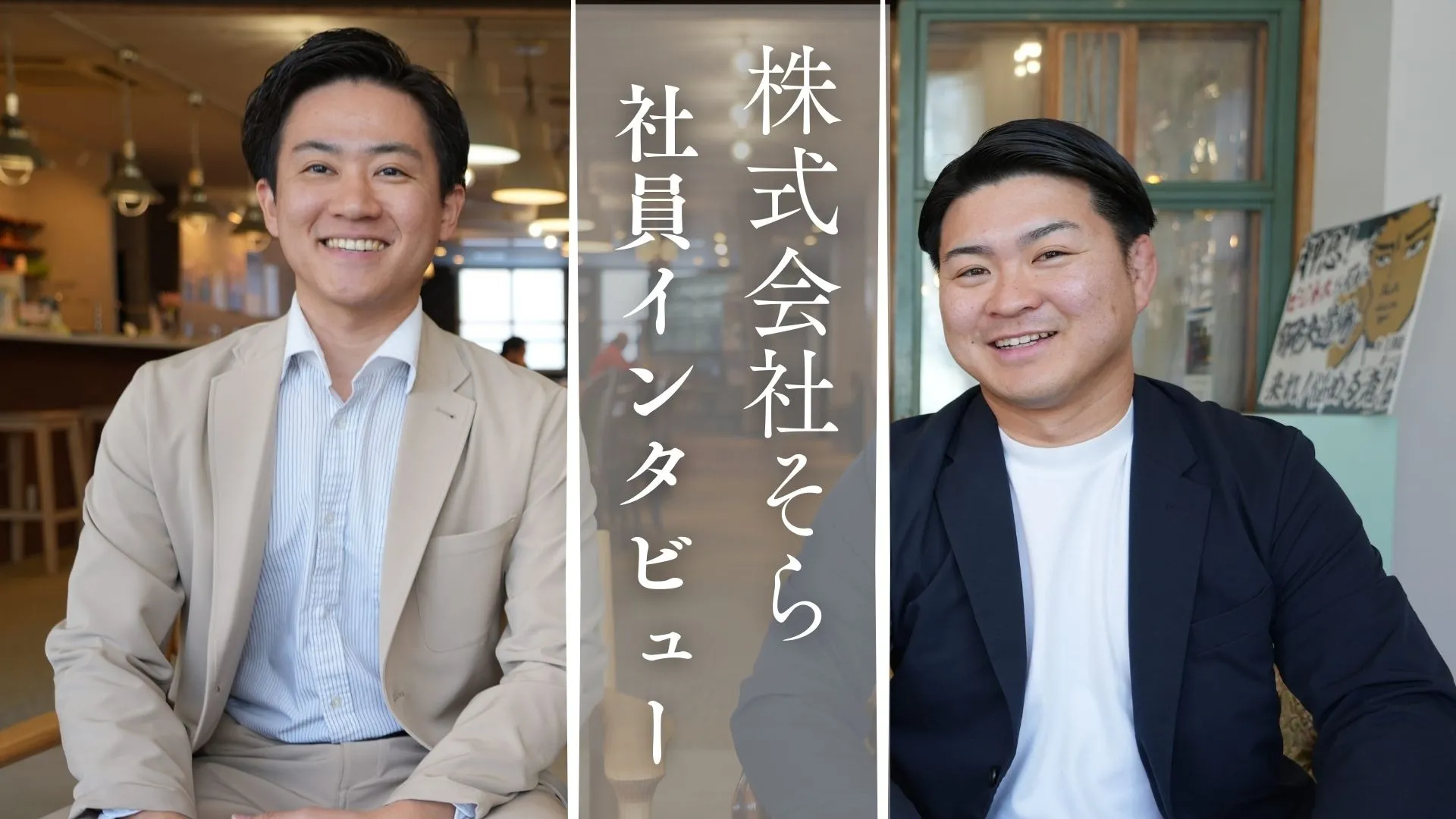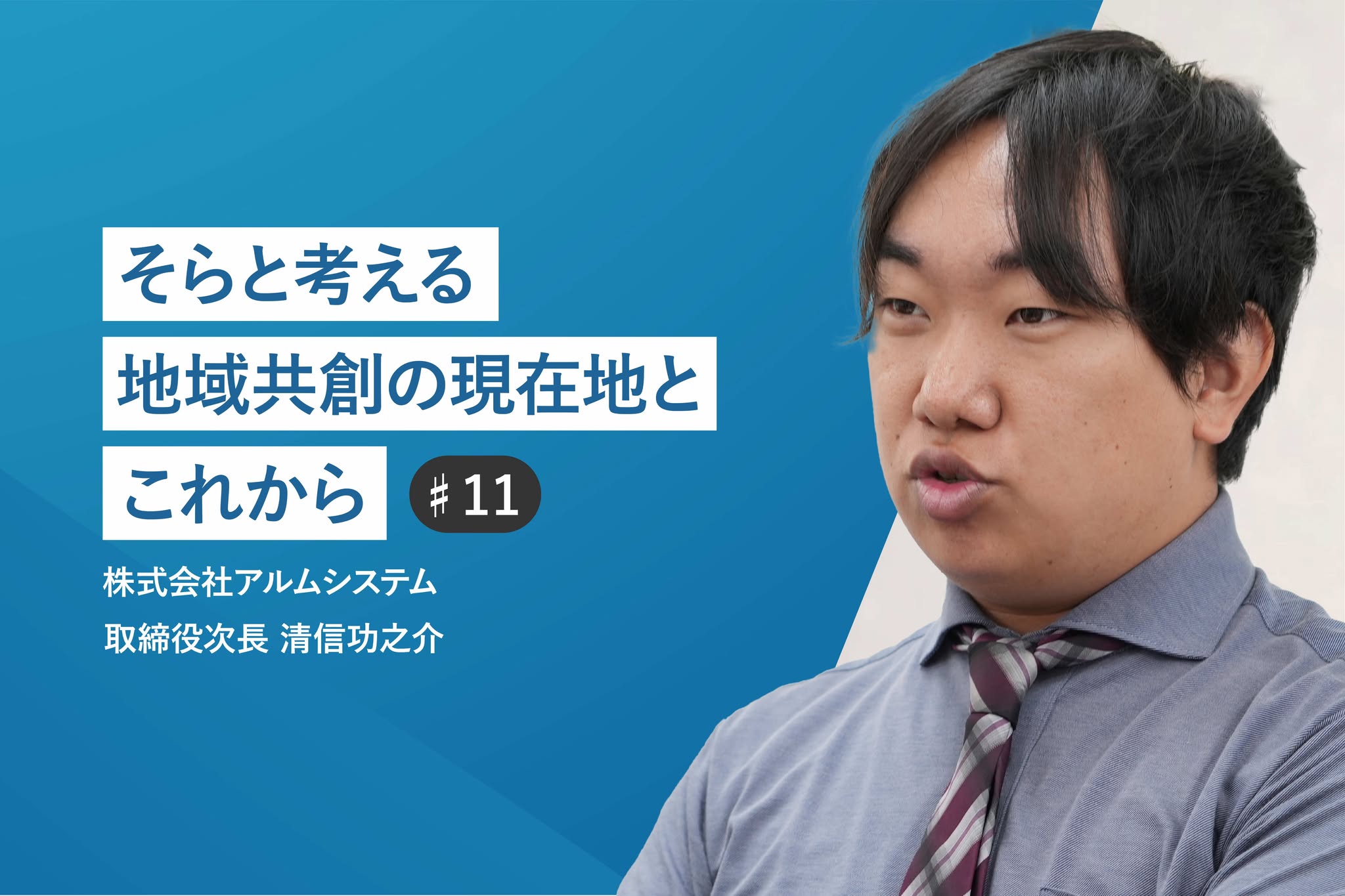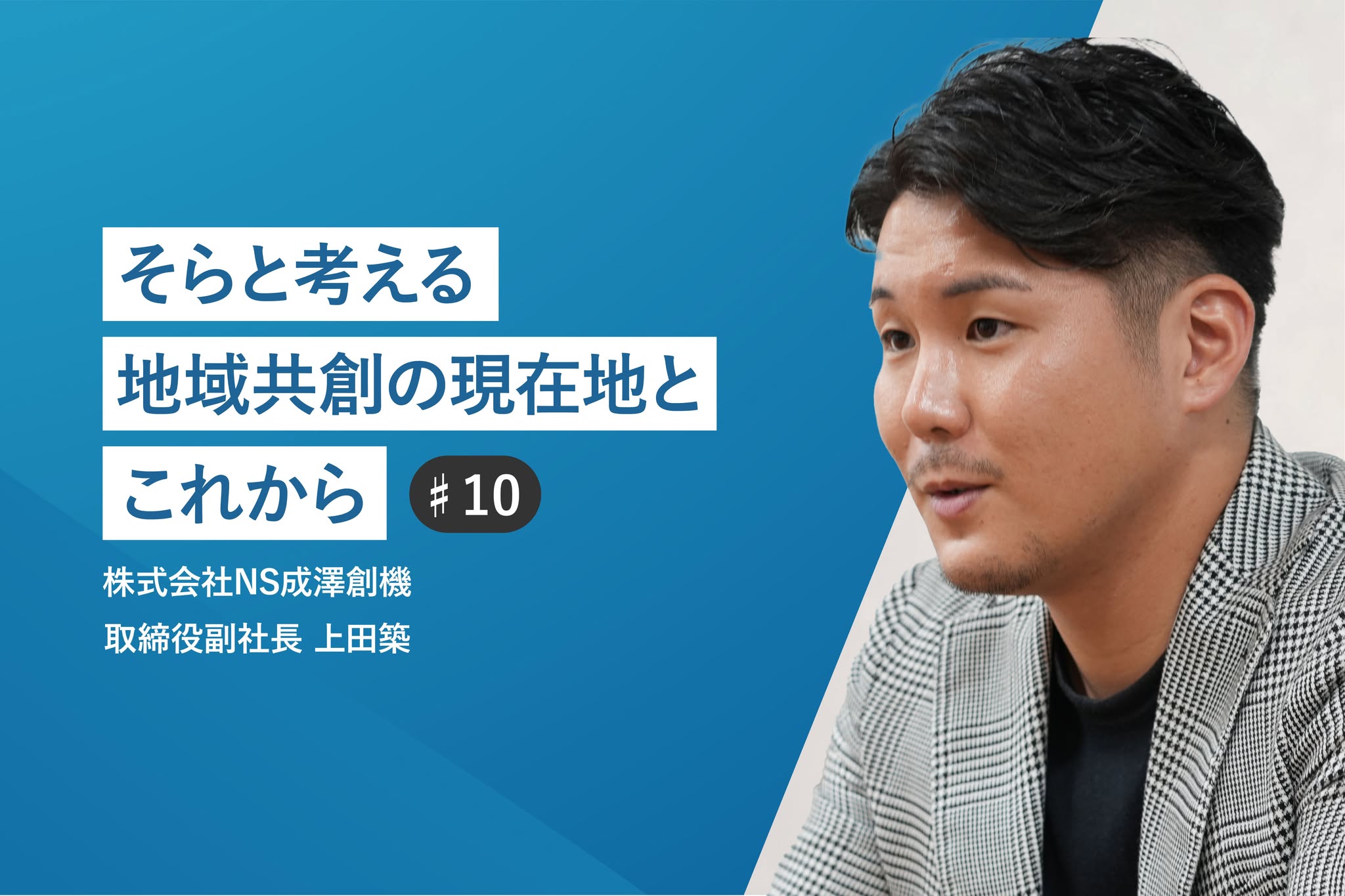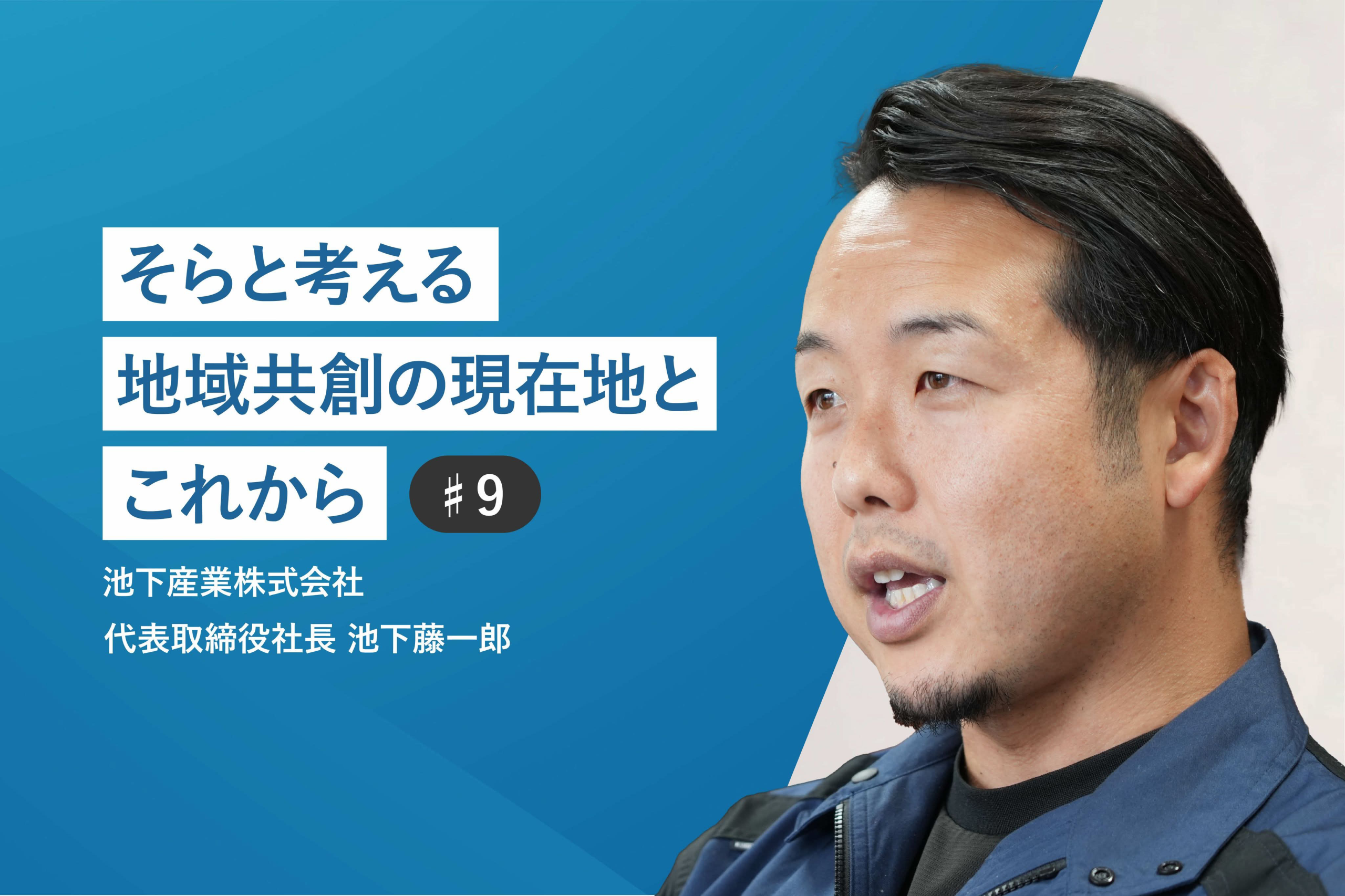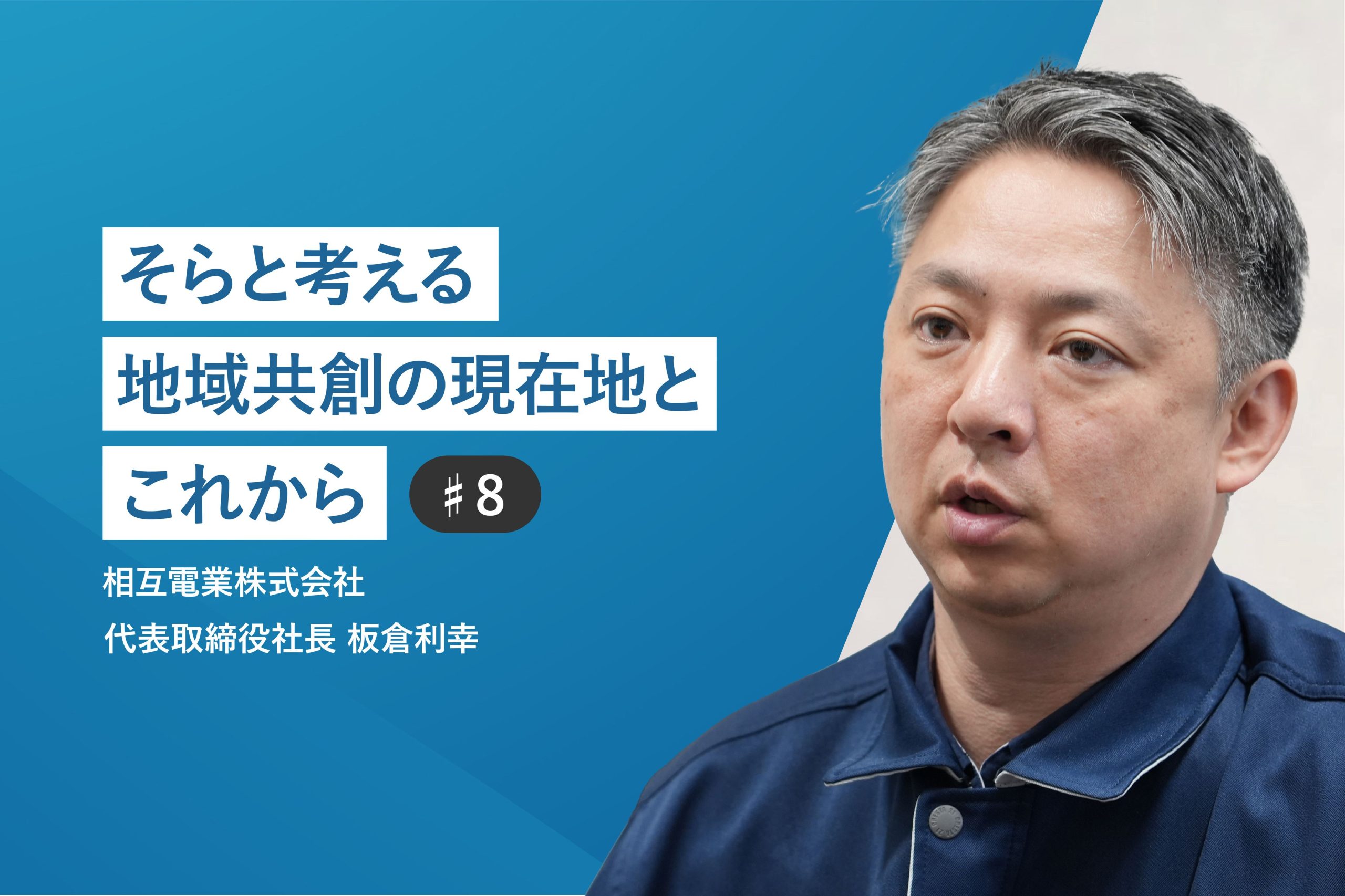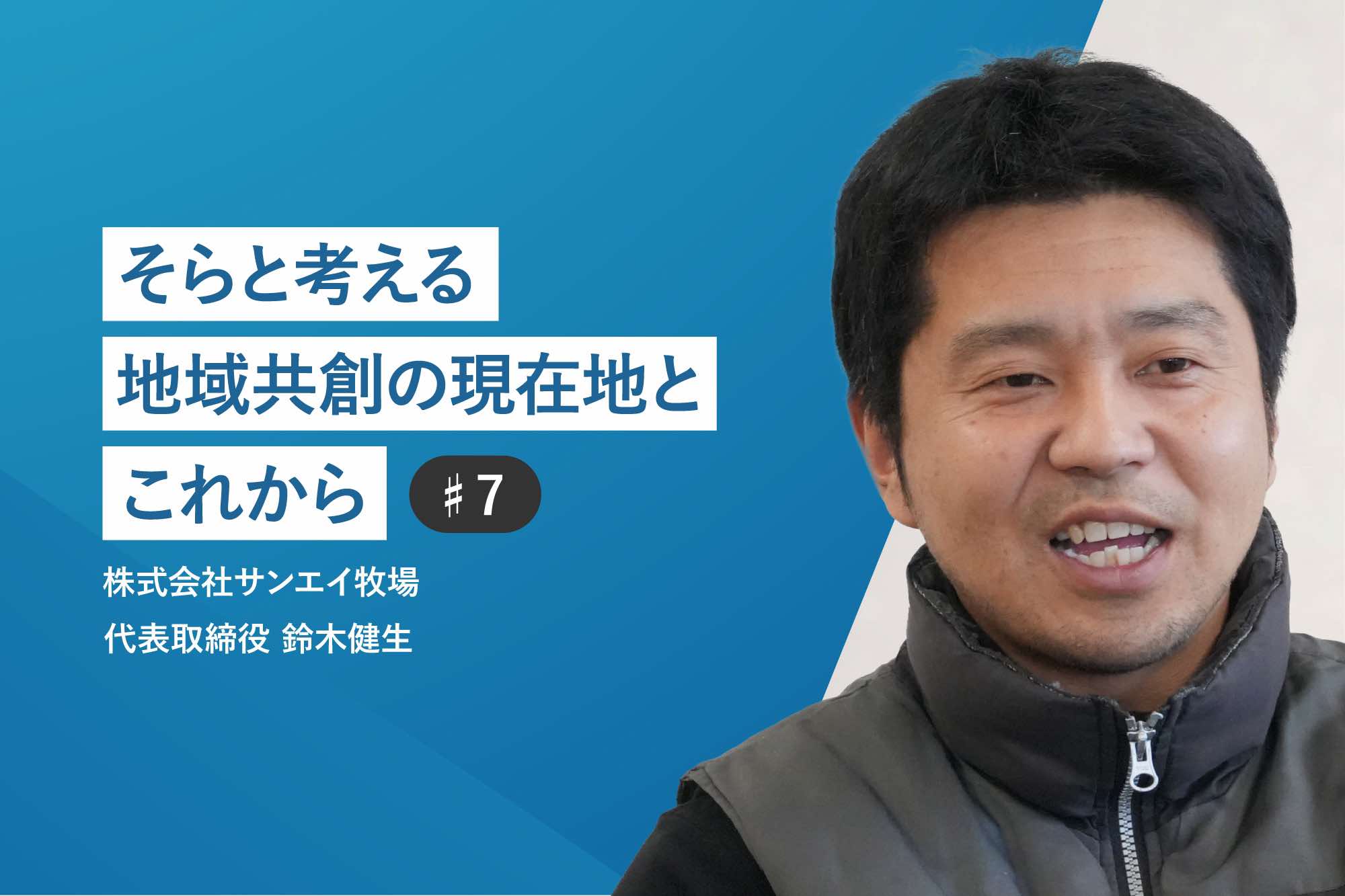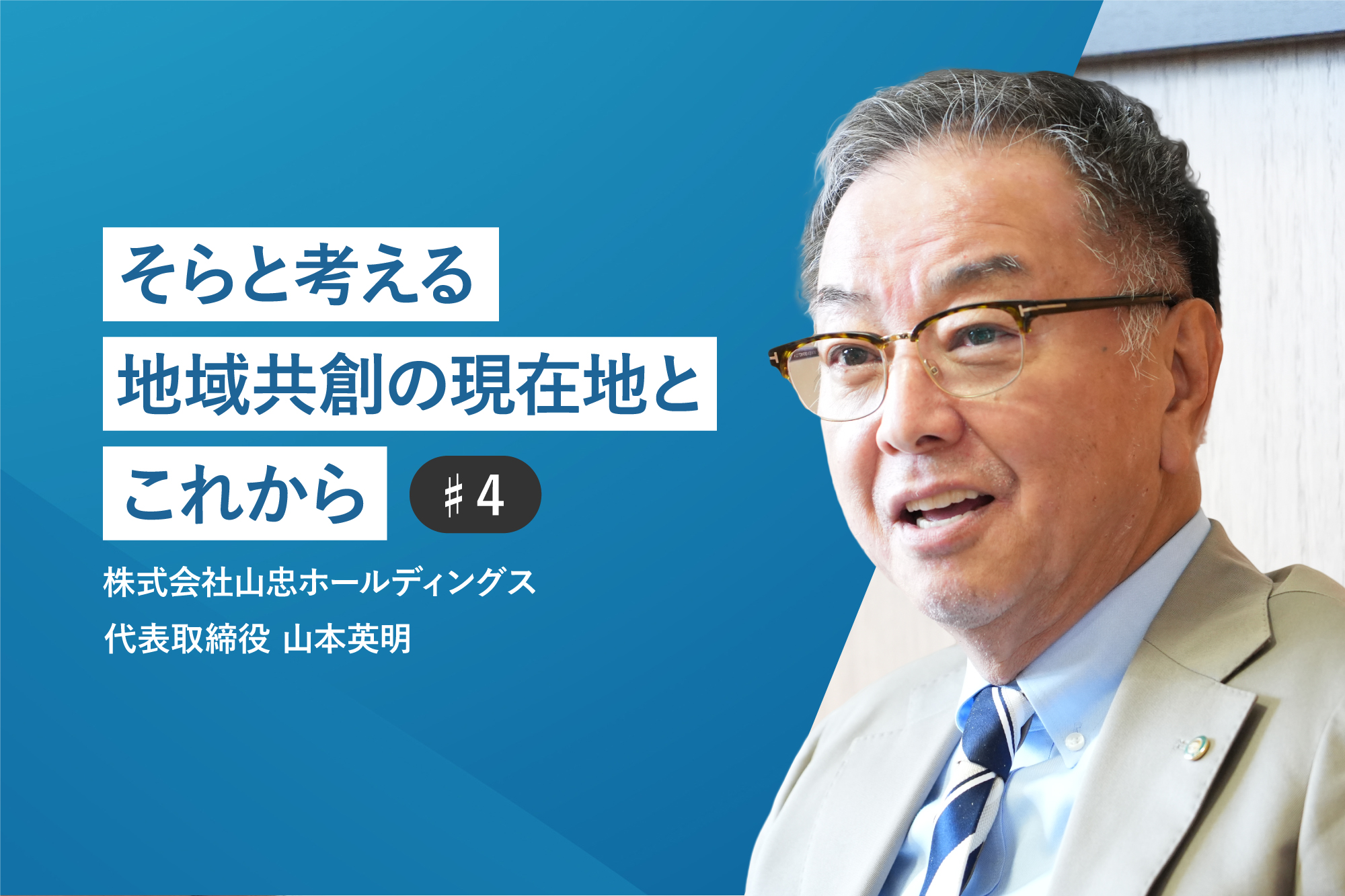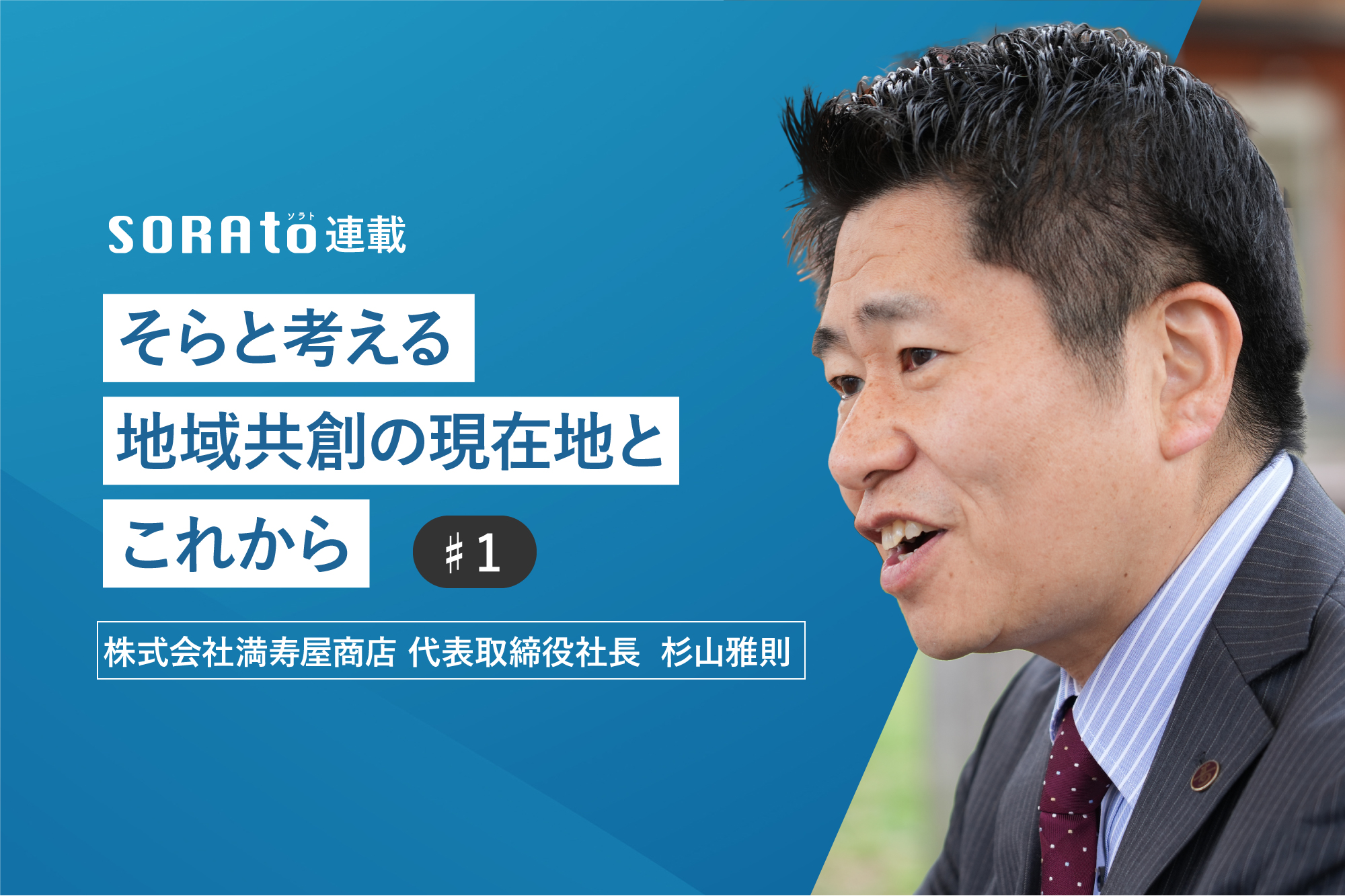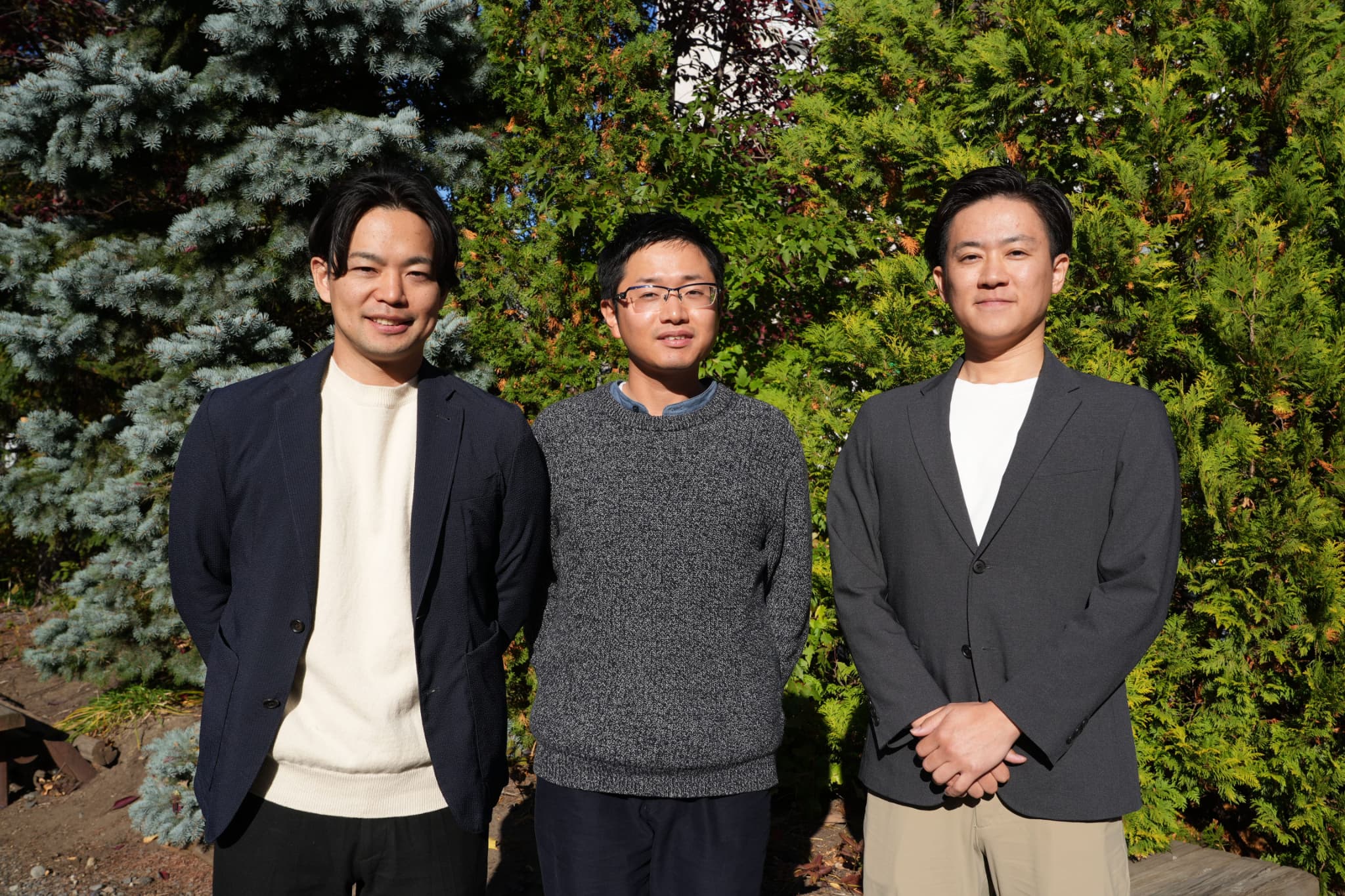
第十二回目のフロントランナーは、帯広市で120年続く農業を受け継ぐ、株式会社まぶちファームの四代目・馬渕裕貴氏(33)。東京でコンサルタントとしてキャリアを積み、Uターン後は「農家から農産業へ」を掲げ、データ活用とチーム経営による新しい農業モデルの構築に挑んでいます。
家業に戻るまでの経緯、父と共に始めたチーム農業の現場、そして十勝という地域が持つポテンシャルまで──。三浦豪・秦翔悟両氏が、次世代の農業と十勝の未来について伺いました。
(取材:株式会社そら 三浦豪/秦翔悟 記事・写真:スマヒロ編集部)
PROFILE
1992年生まれ、北海道帯広市出身。帯広柏葉高校、明治大学法学部卒。2014年に大和総研ホールディングス(現・大和総研)へ入社し、金融系システムの設計に従事。その後PwCコンサルティングで金融セクター支援、早稲田大学大学院でMBAを取得。KPMGコンサルティングでは脱炭素経営やスタートアップ連携を担当。2023年2月、Uターンして家業の株式会社まぶちファームに参画。
畑のある日常──原点にある農業一家の風景


馬渕さんが幼い頃は、お父さんとおじいさんでまぶちファームを運営されていたんですか?

そうですね。基本的には父が中心で、祖父はサポート的な立場でした。

家業の手伝いなどはたくさんやりましたか?

「手伝ってほしい」と言われたことは全くなかったです。ただ外に出れば畑があるので、自然と何かしらやることがあるんですよね。ジャガイモを選別したり、長芋を掘ったり。“手伝い”というより、当たり前のこととして少しだけ関わる、そんな感覚でした。「将来やりたいからやる」といった意識も特になかったですね。

ご両親の仕事を見ていて「大変そうだな」と感じることはありましたか?

父が農業で、母は北海道職員の公務員でした。今も定年後の再雇用で、北海道農業大学校に勤めています。だから、小さいころから“公務員の仕事”と“農業の仕事”の両方を見ていたんです。ただ、どちらが大変とか、優劣があるとは感じませんでした。
東京で見た世界──農業とは無縁のキャリアへ

大学では東京に出られて、NPO活動をされていたとうかがいました。

学生団体のNPO「アイセック(AIESEC)」に所属していました。海外の人を日本に呼んだり、日本の学生を海外のインターンに送り出したりする国際団体です。留学や法律事務所でのアルバイトもしており、当時は“ガクチカ”の延長というか「いろんな経験を積んでおこう」という気持ちが大きかったですね。
大学は明治大学でしたよね。その時点で「いずれは家業を継ごう」という意識はありましたか?

まったくなかったです。本当にゼロ。完全に農業とは関係のないキャリアを歩むつもりでした。大学を出て東京で就職し、キャリアを積むのが自然だと思っていましたね。
普通に企業に就職して、コンサルティングファームを2社経験しました。その間にMBAの取得もしましたね。当時はコンサル人気が高くて、自分は新規事業開発を担当していました。「新しい事業をつくる」という仕事に惹かれていましたね。
そこから農業へ、というのは大きな転換ですよね。

そうなんです。新規事業をつくる仕事をしているうちに「自分でも事業をやってみたい」という思いが強くなっていきました。たまたま実家が農業をしていたので「やってみたら面白いかも」と感じたんです。“継ぐ”というより「自分の事業として挑戦してみよう」と思ってUターンしました。
父と子でつくる“チーム農業”──現場を動かす学生たちの力


今はお父様と一緒にまぶちファームを運営されているんですよね?

はい、基本的には二人でやっています。以前は従業員もいましたが、父が引退を見据えて規模を少し縮小していた時期がありました。その流れで機械や土地も整理していたんですが、私が戻ってきたことで「もう少し頑張れるかも」となって。
現在は父と私の二人を中心に、時期ごとに学生アルバイトを加えて運営しています。

学生アルバイトを採用しているんですね。

はい。寮に住む学生を中心に全体で20人ほどに協力してもらっています。収穫期などの繁忙期には、その中から5〜6人ずつシフトを組む形です。
バイトリーダーを1人置いて、その人を中心にスケジュールを任せています。私が直接声をかけるのではなく、リーダーが寮の中で仲間を集めてくれる。部活動みたいなノリで、自然と上下関係もできていて、作業の指導を学生同士でしてくれるんです。
今はアプリで人材を集める農家さんも多いですが、うちは学生ネットワークがあるので、人手不足はほとんど感じていません。
Uターンで見つけた新たな十勝の価値──客観的に見える“強み”とは


十勝は、一般的には“田舎”と言われることも多いと思います。東京で暮らしてみて、あらためて地元のことをどう感じましたか?

実際に十勝に戻ってみて感じたのは、家族と暮らす視点で見たときの住環境の良さです。それに、仕事面でも東京ほど競争の圧力が強くない。その分、伸び伸びと自分のペースで働けて、結果的にパフォーマンスを発揮しやすい環境だなとも感じました。
これまでにも東京の企業の方を十勝にアテンドする機会があったと思うのですが、そうした場で「十勝のポテンシャルの高さ」を伝えるときに、意識していることはありますか?

自分が東京にいた経験があるからこそ、“十勝びいき”にならない視点を持てたのは大きいです。ずっと地元にいると「十勝は最高!」って主観で話しがちですが、外から来た人にとっては、それが“地元ひいき”に聞こえることもある。
だからこそ、あえて「客観的な立場」で見て、十勝が本当に優れている点をロジカルに説明できるようにしてきました。
たとえば脱炭素の実証事業を進めるにしても、農業分野のパートナーが多く、フットワークが軽い人も多い。だから「実証をやるには最適な場所ですよね」と伝えられるんです。
実際、自動車メーカーから「脱炭素関連の機械を試作して動かしてみたい」という相談を受けたこともあります。そういう機械を「実際に使ってくれる人」がこれだけいるのは、十勝くらい。だから「ここでやる意味がある」と自信を持って説明できる。

上士幌町の自動運転の実証実験などもそうですよね。人口が少なく、土地が広い。だからこそ「必要とされる技術」がある。

そうですね。補助金や支援が積極的で、動きの早い自治体パートナーもいる。こうした条件がそろっているのは、実は十勝くらいなんです。だから十勝を「特別視」して伝えるのではなく、客観的に見て良いところを説明できるかが大事だと思っています。
農家から農産業へ──優秀な人材が集まる仕組みをつくりたい

日本の人口が減っていく中で、一次産業に従事する人も減少しています。そうしたなかで、農業王国「十勝」が果たす役割はますます大きくなっていくはずです。これからの農業についてどのように考えていますか?

現状、有名大学を出た人や、ある程度キャリアを積んだ人の中で「農業」を最初から選択肢に入れている人は少ないと思います。だからこそ、0.1%でもその割合を増やしていくことが大事だと感じています。
「農業」と聞くと「農家」という言葉が先行しますし、「大変そう」「泥臭い」といった印象もまだ根強い。でも実際は、農業って製造業に近い仕事なんです。様々な工程で大きな機械や装置を使います。
意外かもしれませんが土壌も“生産設備”と見立てられます。植物が育つためにカルシウムやマグネシウムなどを土壌に加えていく作業は、製造工程そのものです。
そう考えると、農業のイメージが少し変わりますね。

はい。だから私は「農家から農産業への移行」を、小さくても実現したいと思っています。農業が産業として認知されるようになれば、若い人も職業として選びやすくなる。仕事内容も、体を動かす仕事と考える仕事が半々くらいになるのが理想です。
でも今はどうしても、経験したことがない人から見ると“鍬(くわ)を持つ人”という肉体労働の側面が先行してしまって、社会的な地位が上がりにくい。そこを少しずつ変えていきたいですね。
農業という仕事の中で「考える仕事」の比率を高めていくということですね。

そうですね。どの産業でも同じですが、効率や品質を考えて行動できる人が増えれば、生産性は確実に上がります。
しかし、農業では「経験と勘」の世界が多く残っていて、それが新しい人材にとっての参入障壁にもなっている。だからこそデータや仕組みを使ってチームで回せる体制──いわば「仕組みで動く農業」を実現したいと思っています。
そうやって産業としての農業の形を整えていくことで、新しく挑戦する人も増えていくと思うんです。
十勝に戻る理由、来る理由──実体験を伴う“誇り”と“リアリティ”を伝えていく

「農業に人が入ってこない」という話がありました。そもそも馬渕さんのように、十勝にUターンしてくる人ってどれくらいいる印象ですか?

正直、かなり少ないと思いますね。みんな「戻りたい気持ち」はあっても、実際に戻るとなると仕事や収入の問題が大きい。たとえば東京でキャリアを積んだ人が、そのまま横スライドして同じ経済的水準を保つのは難しいんです。それが「戻れない理由」になっているケースが多いと思います。

確かに、一度積み上げたキャリアをリセットするような感覚になってしまうんですね。

そうなんです。リセット感があるんですよね。「戻ったら給料が下がる」「同じレベルの仕事がない」と感じてしまう。でも実際に住んでみると、3年くらいで「意外とやっていける」と気づく人が多いんです。
ただ、その“リアリティ”を事前に伝えるのが難しい。言葉だけではなかなか伝わらないんですよね。
なるほど。十勝を“働く場所としての魅力”として伝える仕組みが、まだ足りていないと。

そう思います。「自然がきれい」とか「食べ物がおいしい」っていうのはもちろん大事ですけど、それだけでは戻る理由にはならない。「十勝でも稼げる」「東京と同じようにビジネスができる」そうした「現実的な良さ」をもっと発信していくことが大事だと思います。
確かに。リモートワークの普及で、都会との距離のハードルも下がってきていますしね。

そうなんです。実際、東京の企業とオンラインで連携して仕事を進めるケースも増えました。「距離があるからできない」という時代ではもうない。むしろ、環境や人の余白がある分だけ、新しいことを試しやすい。そういう意味で、十勝は挑戦に向いている土地だと思います。
「東京に行かないと成長できない」という価値観は、もう変わりつつありますよね。

ええ。だからこそ「十勝で働く」「地方で暮らす」ことを「豊かな選択肢」として伝えていきたいんです。その壁を取っ払い「他の人もそう言ってるし、確かにそうかも」と思えるような共感を生む。誇りを取り戻すというか、そこに“価値”を付けて発信していくのはすごく重要だと思います。

まさに“人とお金を地域に呼び込む”という、私たち「そら」のテーマにも通じますね。

だからこそ、まずは身近な人たちが「ここ、意外といいよ」って感じられる状態を作る。それが最初の一歩になると思います。
(取材:株式会社そら 三浦豪・秦翔悟/記事・写真:スマヒロ編集部)
PROFILE
株式会社dandan 代表取締役 | PwCの戦略コンサルティングチームStrategy&、ベンチャーキャピタルの Reapraグループを経て、2021年に株式会社dandanを創業。人や組織は「だんだん」変容するというコンセプトで、企業研修や経営支援、コンサルティングを行っている。2023年に帯広市に移住したことをきっかけに、SORAtoインタビュー企画のディレクターとしても活動している。
PROFILE
群馬県高崎市出身。1996年生まれ。東京農業大学第二高等学校(群馬県高崎市)、成城大学卒業。その後フィリピン語学留学。台湾の大学院に進学。経営学修士を取得後の2022年に三井住友ファイナンス&リース入社。2025年2月、株式会社そらにジョイン。