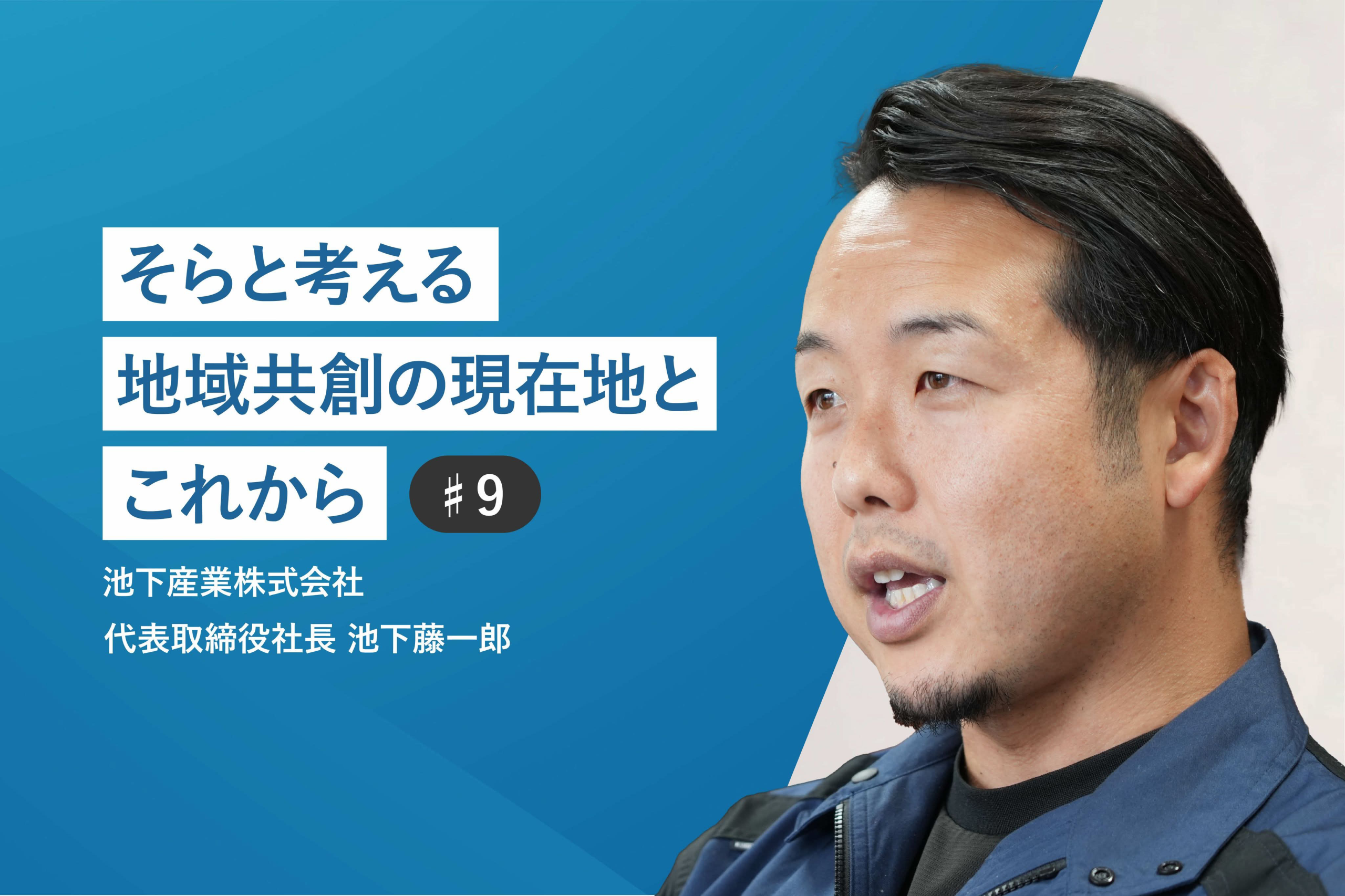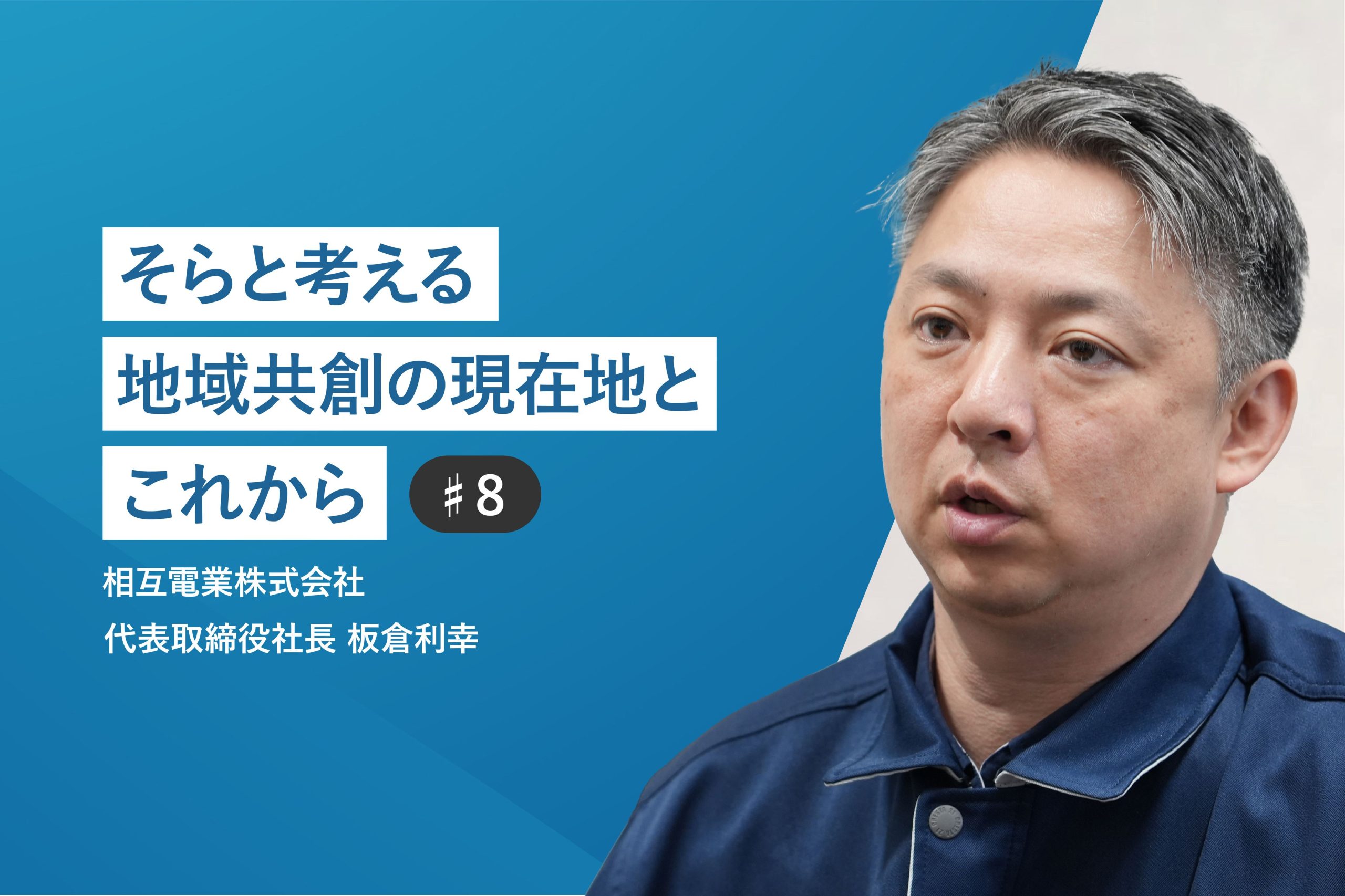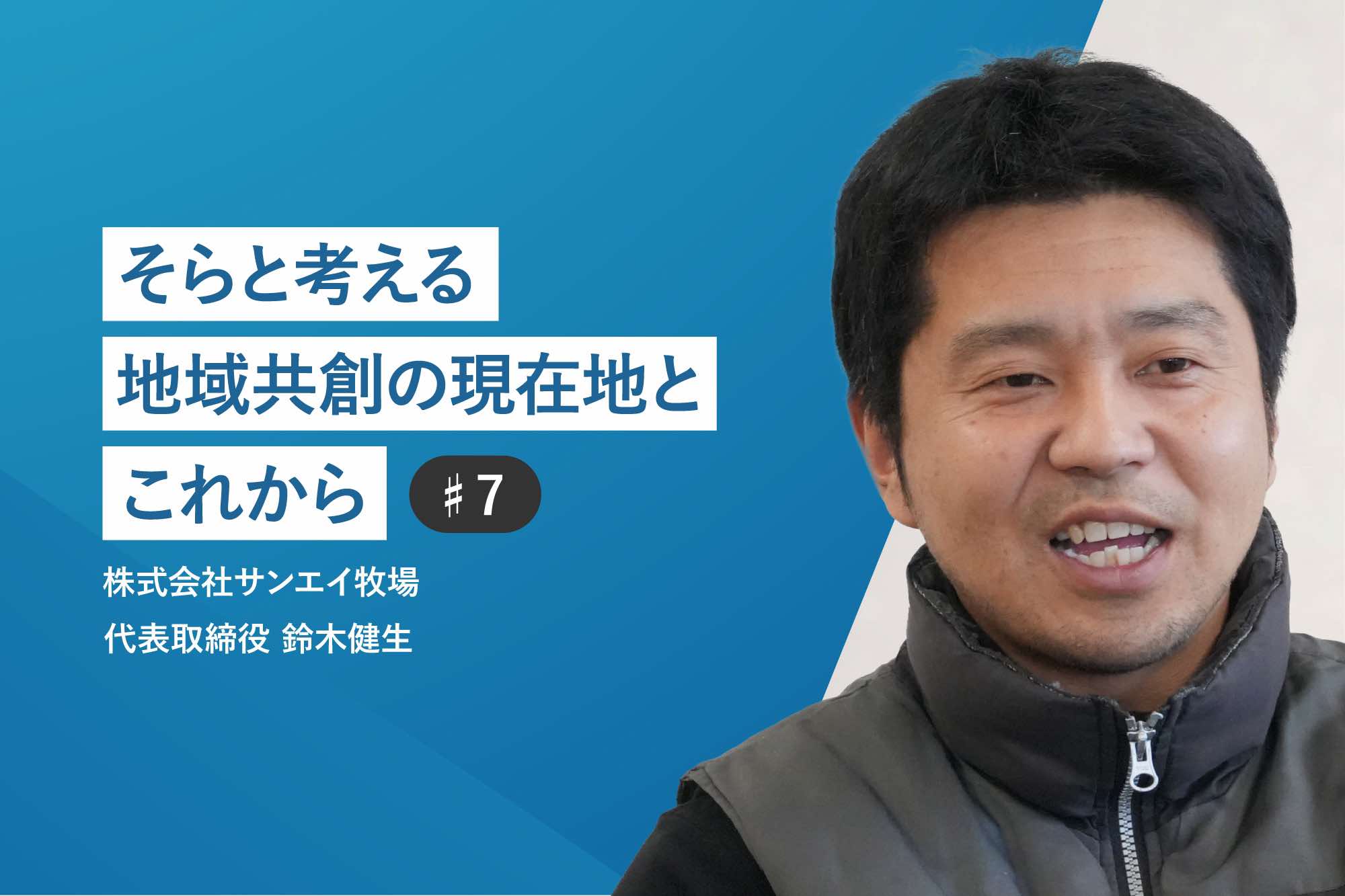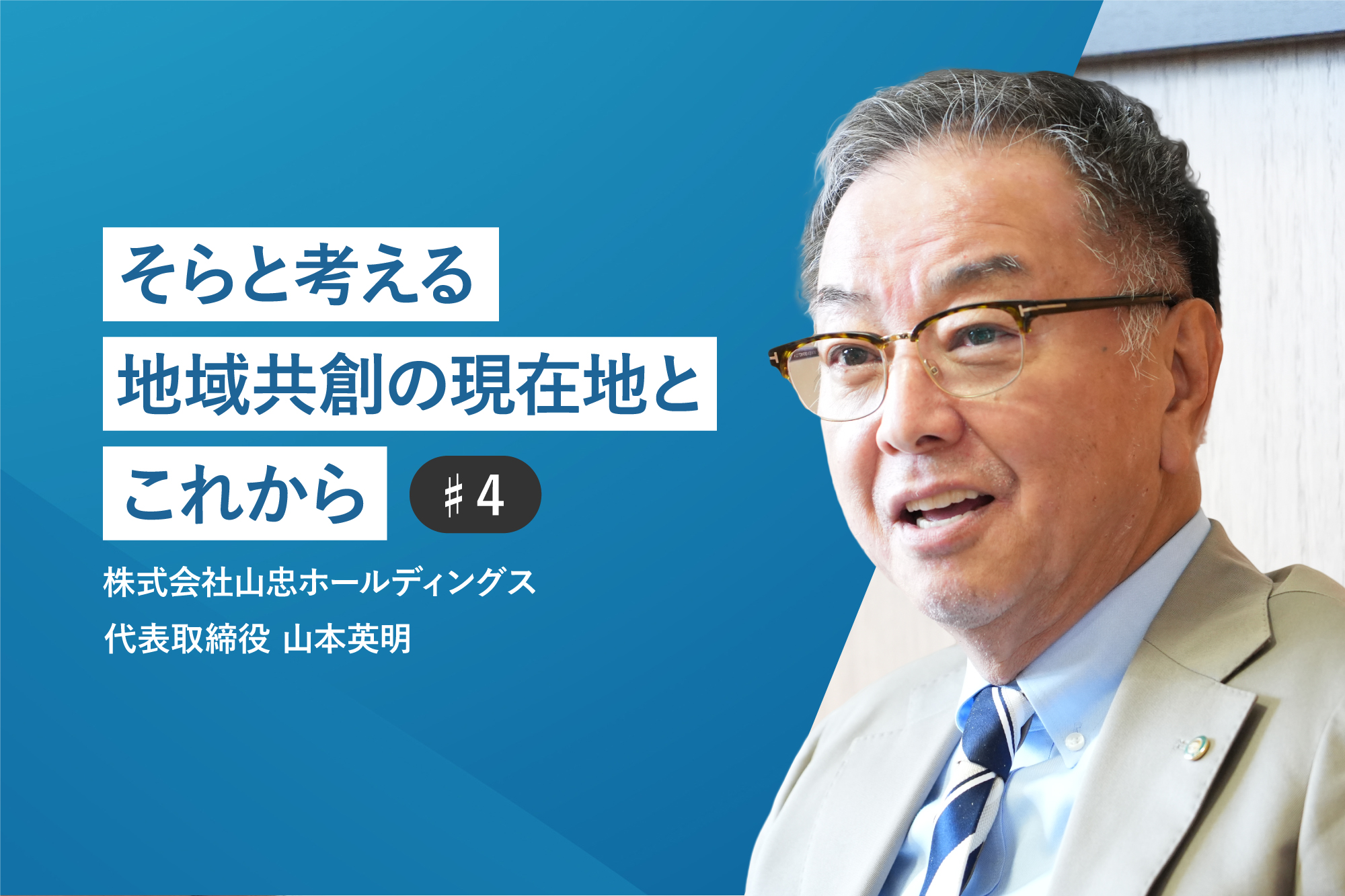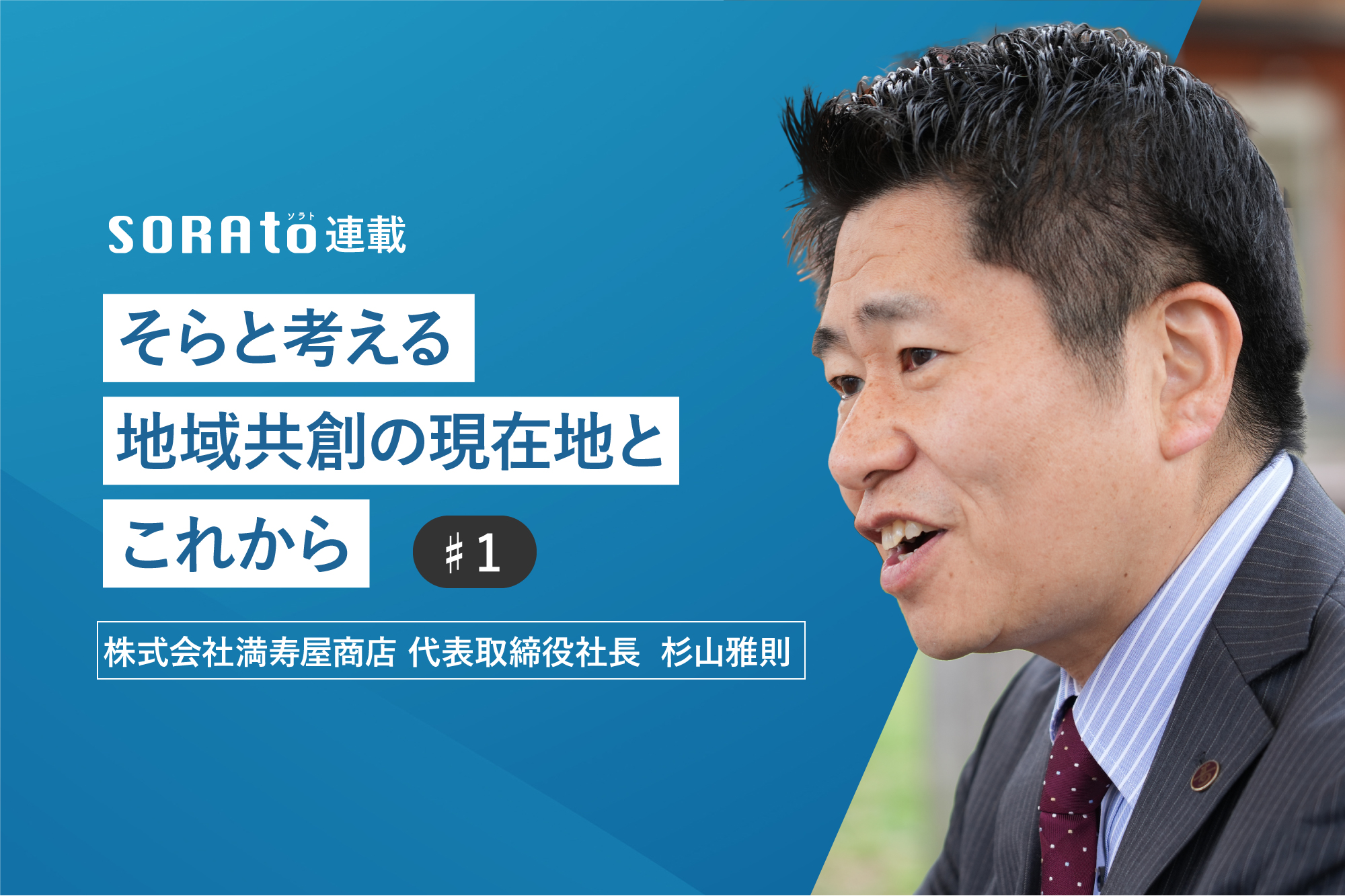第十回目のフロントランナーは、帯広を拠点に建築鉄骨の設計・製作・建方までを担う株式会社NS成澤創機の取締役副社長(取材時は常務取締役)・上田築(うえだ きづく)氏(30)。モンテネグロ1部FKデチッチの元プロGKという異色の経歴を持ち、商社での8年の修行を経て2024年にUターン。ロボット化の進む鉄骨工場で「強い現場」をつくり、地域に“倒れない品質”を提供する―その視線の先にある、十勝の産業と人づくりの未来を伺いました。
(取材:株式会社そら 三浦豪 / 加藤直樹 記事・写真:スマヒロ編集部)
PROFLE
1995年生まれ、帯広市出身。帯広北高、仙台大学(休学)。ゴールキーパーとして欧州モンテネグロリーグ・モンテネグロ1部FK Decic(デチッチ)に在籍。帰国後は国内Jクラブからの打診も受けつつ、将来を見据え商社(JFE商事)で8年勤務し、素材調達・価格交渉の実務を習得。2024年2月に家業であるNS成澤創機へ。2026年1月現在は取締役副社長として営業・資材調達・生産計画に携わる。趣味はゴルフ。
“止めることがカッコいい”─GK少年が見たプロの現実と、十勝を離れて見えたもの


まずは原点から。サッカーとの出会いは?

柳町小の2年で本格的に始めて、最初からGKでした。フットサルのPKで止めた快感が忘れられなくて(笑)。2002年の日韓W杯をテレビで観て、「プロになる」と決めたのもこの頃です。共栄中では帯北アンビシャスの1期生、帯広北高では3年時に北海道ベスト4。仙台大でも1年から試合に出場していました。

海外で挑戦もされたのですね。

大学在学中に欧州のスカウトに声をかけられ、セルビアのクラブへ。3年半在籍しましたが、給与未払いでチーム全体がボイコットする日もある。クラブハウスに行っても誰も来ない。そんな環境で、生きるための逞しさや、日本の当たり前のありがたさを骨身に染みて学びました。


帰国後の進路は大きな決断でしたか。

Jの下部からの話もありましたが、条件や将来像を冷静に考えたとき、別の道を選びました。サッカーで培った集中力や準備力を生かす場所は、競技以外にもあるはずだと。
「継がない」と言い続けた家業へ──商社8年で掴んだ“材料の論理”


家業に戻る前に商社で8年。狙いは?

鉄骨の世界は、とにかく材料コストの比重が大きい。切る、開ける、溶接する技術があっても、鋼材の仕入れで勝てなければ現場は苦しい。そこで、まずは“材料の論理”を体で覚えるべく商社に入りました。相場の読み方、サプライヤーとの交渉、数量と価格の関係……毎日が実戦でした。

もともと家業を継ぐ気はなかった?

正直、若い頃は父に「継がない」と宣言していました。業種すらよく分かっていなかった(笑)。でも海外とビジネスの現場を経験して、「自分の土台」をつくる意味で家業に向き合う覚悟ができた。予定より長く8年になりましたが、今はその遠回りが効いていると感じます。
ロボットが走り続ける工場─“倒れない品質”をつくる現場力


NS成澤創機の事業を改めて教えてください。

建築物の骨組みとなる鉄骨を加工し、現場で建てるまでを担います。丸や四角の柱・梁となる鋼材を仕入れ、切断・孔開け・溶接を経て製品化。大物はロボットで24時間回し、細部は熟練工が仕上げます。7年前に帯広・幸福エリアに新工場を建て、国土交通大臣認定のHグレード(いわゆる上位グレード相当)も取得。これで受注の“上限”が外れ、お客様が大型案件を取った際にも地域内で完結できる体制が整いました。

現場の改革で重視していることは?

“倒れない品質”を当たり前にすること。建物は人の命と事業を守る器です。DXやAIで工程は賢く、でも最後は人の眼と手。可視化・標準化と、職人の直感の両輪で品質管理を徹底しています。
価格は生き物。勝負は「仕入れ」と「読み」─サッカー脳が効く


担当領域は?

営業と資材調達が主戦場です。鋼材は相場商品で、月単位で動く。同じ仕様でも、仕入れ方で原価はまったく変わる。取引先の生産状況、在庫、物流、為替、そして案件の山谷を読み、どのタイミングでどこから、どの資材を、どれだけ押さえるか。ゴールキーパーの“状況判断”がそのまま生きています。

交渉の妙もありそうです。

こちらの仕事量や継続性をどう示すかで価格は動きます。単価の1割が数百万円規模で効いてくる世界。勝つべきところで勝ち、引くべきところで無理をしない。その判断の質を上げ続けたいですね。
人が足りない業界を“持続可能”に─採用・育成・働き方のリアル


人材面での課題は?

業界イメージは「重労働・休めない」。実際は大型・ロボット化が進み、現場も安全第一で改善が進んでいますが、完全週休二日が難しい工程も残る。高卒の新卒は定着が難しい一方、専門卒やUターン・中途は腰が据わりやすい傾向です。だからこそ、業界全体で働き方のアップデートを急ピッチでやらないといけない。採用には投資していますし、教育は“見て覚えろ”から計画的OJTへ切り替え中です。
設備投資は“読み”と“度胸”─加工能力×需要の難しい方程式

今後の投資や成長の描き方は?

難しいのは「どこまで設備投資を先に打つか」。加工能力を上げても、需要の波と合わなければ回らない。とはいえ、大型案件が来たときに“地域で完結できる体制”は守りたい。お客様に「何があっても任せられる」と言っていただける体制づくりと、財務の健全性―この二つの両立が経営テーマです。

十勝で勝つスポンサーシップ─“払って終わり”から“成果が見える投資”へ

地域との関わりで感じることは?

十勝には各業界のトップクラスの企業が多い。だからこそ、スポーツや文化への協賛が“払って終わり”にならない設計が必要だと思います。どんな成果に結びついたのかが見えれば、企業はもっと気持ちよく応援できる。スポンサーと受け手がWin-Winになる仕組みづくりに、企業側も提案していきたいですね。
“出てよし、戻ってよし”の町に─若者の循環が地域を強くする

十勝で生きる若い世代へメッセージを。

十勝から一度は出たほうがいい。札幌でも、東京でも、海外でも。私も高校卒業後十勝から出たことで、地元の良さを実感することができた。8年住んだ東京も魅力的な場所であったが、十勝にも東京とはまた違う魅力がある。出ないように引き留めるのではなく、「戻りたい」と思わせるまちにすること。仕事・教育・暮らしの“戻れる導線”を企業と地域が一緒に整えるのが、これからの地域共創だと思います。
地域への貢献は“見えない安心”─倒れない建物を静かに支える


地域貢献をどう捉えていますか。

派手ではありませんが、私たちの仕事は“倒れない建物”という見えない安心を提供すること。品質管理を徹底し、当たり前に安全な骨組みを届ける。災害時も、平時も、地域の暮らしと事業を支える陰の主役でありたいと思っています。
未来に向けて─サッカーで学んだ「準備」と「読み」を、十勝の現場へ

最後に、上田さんのビジョンを。

サッカーで身につけたのは、準備と読み、そして状況に応じて最適解を選ぶ胆力です。ロボットと人の最強の組み合わせで“強い現場”をつくり、素材調達の精度で勝ち、地域で大きな仕事を完結できる受け皿になる。十勝の産業はまだ伸びしろだらけ。出た人が戻れる場所にするためにも、NS成澤創機として「品質・納期・安全」で当たり前に勝つ会社であり続けます。
(取材:株式会社そら 三浦豪・加藤直樹/記事・写真:スマヒロ編集部)
PROFILE
株式会社dandan 代表取締役 | PwCの戦略コンサルティングチームStrategy&、ベンチャーキャピタルの Reapraグループを経て、2021年に株式会社dandanを創業。人や組織は「だんだん」変容するというコンセプトで、企業研修や経営支援、コンサルティングを行っている。2023年に帯広市に移住したことをきっかけに、SORAtoインタビュー企画のディレクターとしても活動している。
PROFILE
群馬県前橋市出身。武蔵大学を卒業後、野村證券入社。最初の配属地、とかち帯広営業所でそら代表の米田健史と出会う。その後、大阪の支店で2年勤務。2024年2月、株式会社そらにジョイン。現在は社長室長として社長をサポートする。

今回の主役は、北海道・十勝に移住した三浦豪さん。米国シアトルのワシントン大学を卒業し、世界最大級のプロフェッショナルサービスファーム「プライスウォーターハウスクーパース(PwC)」の戦略コンサルティング...