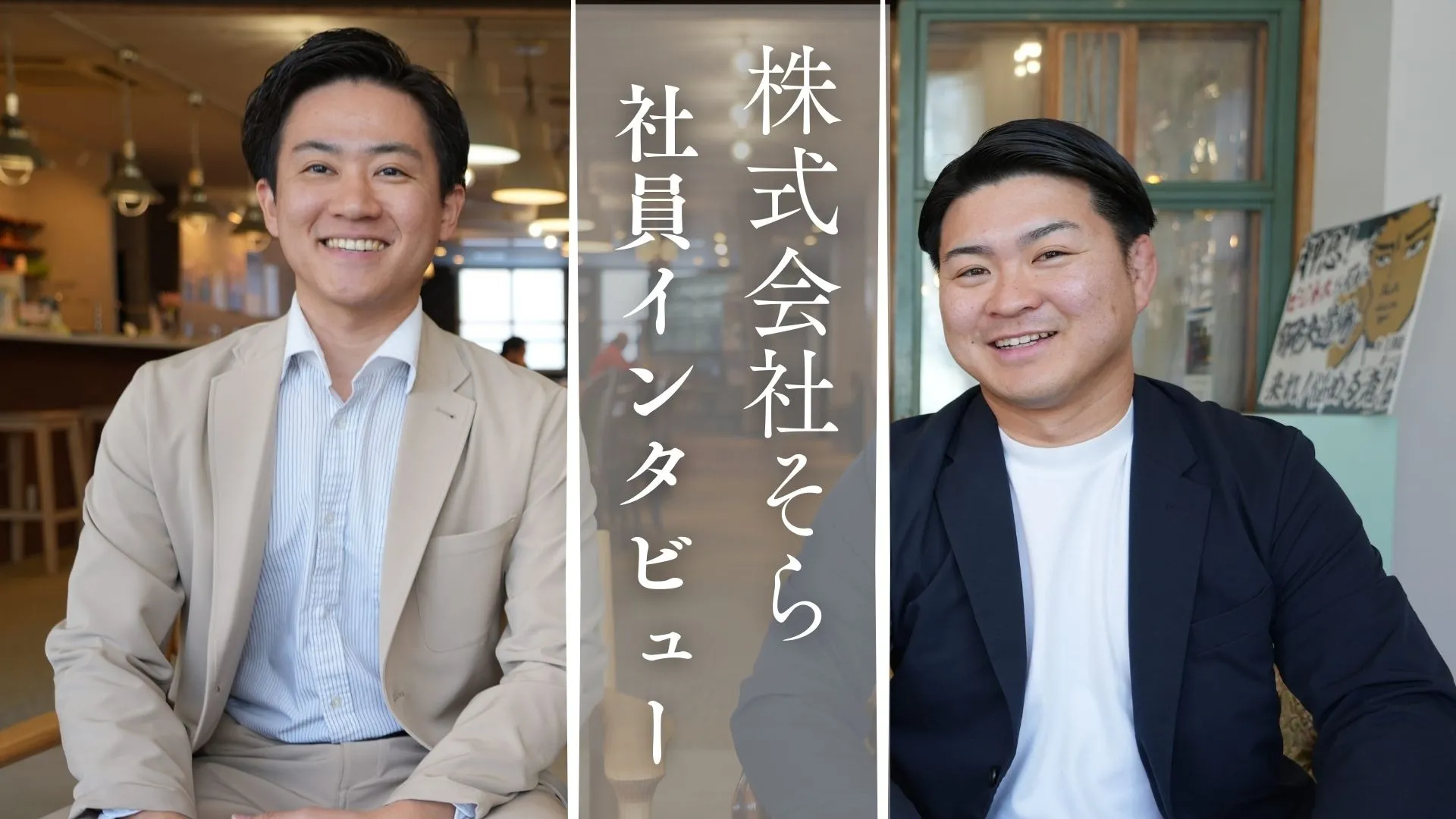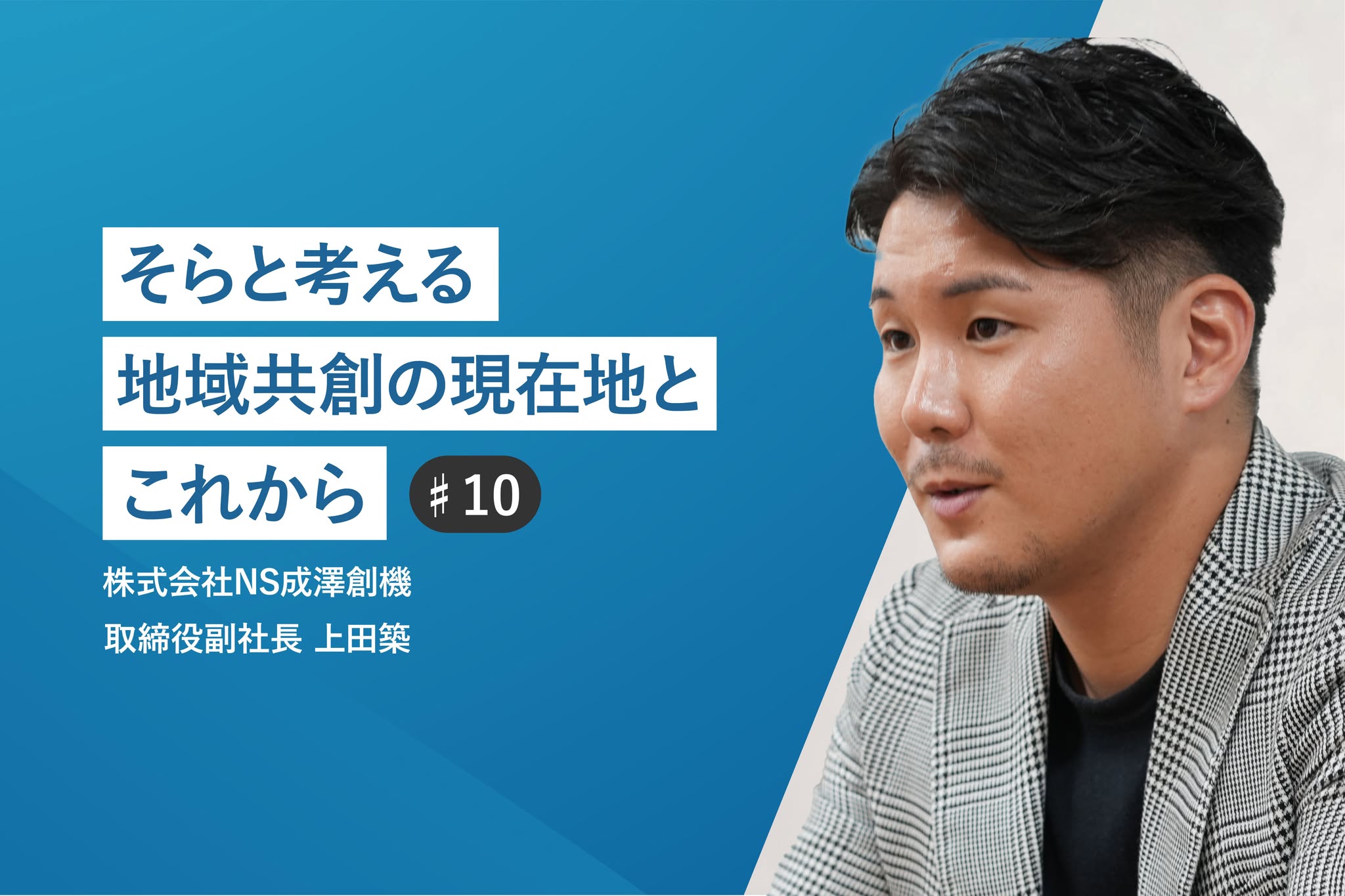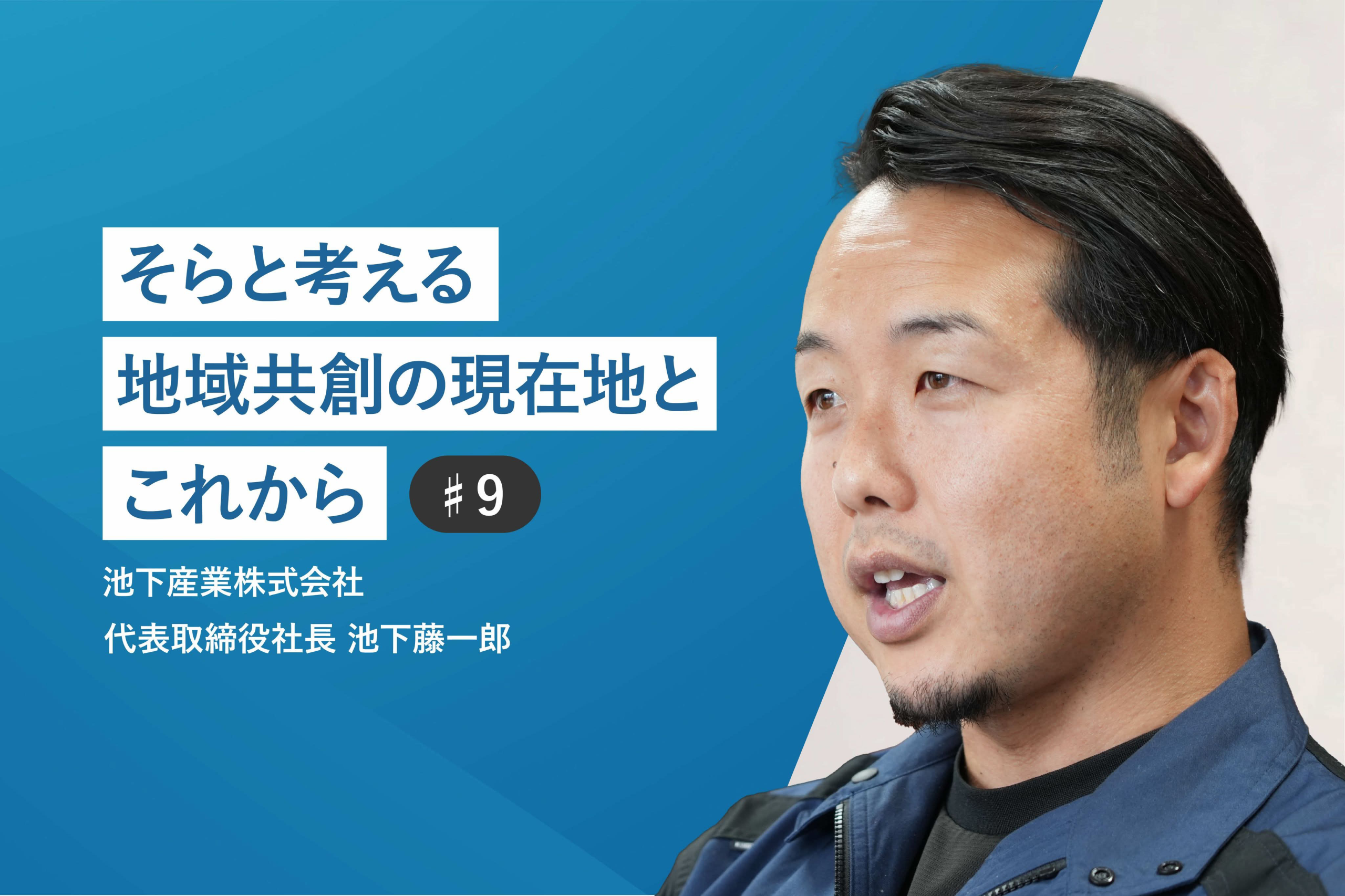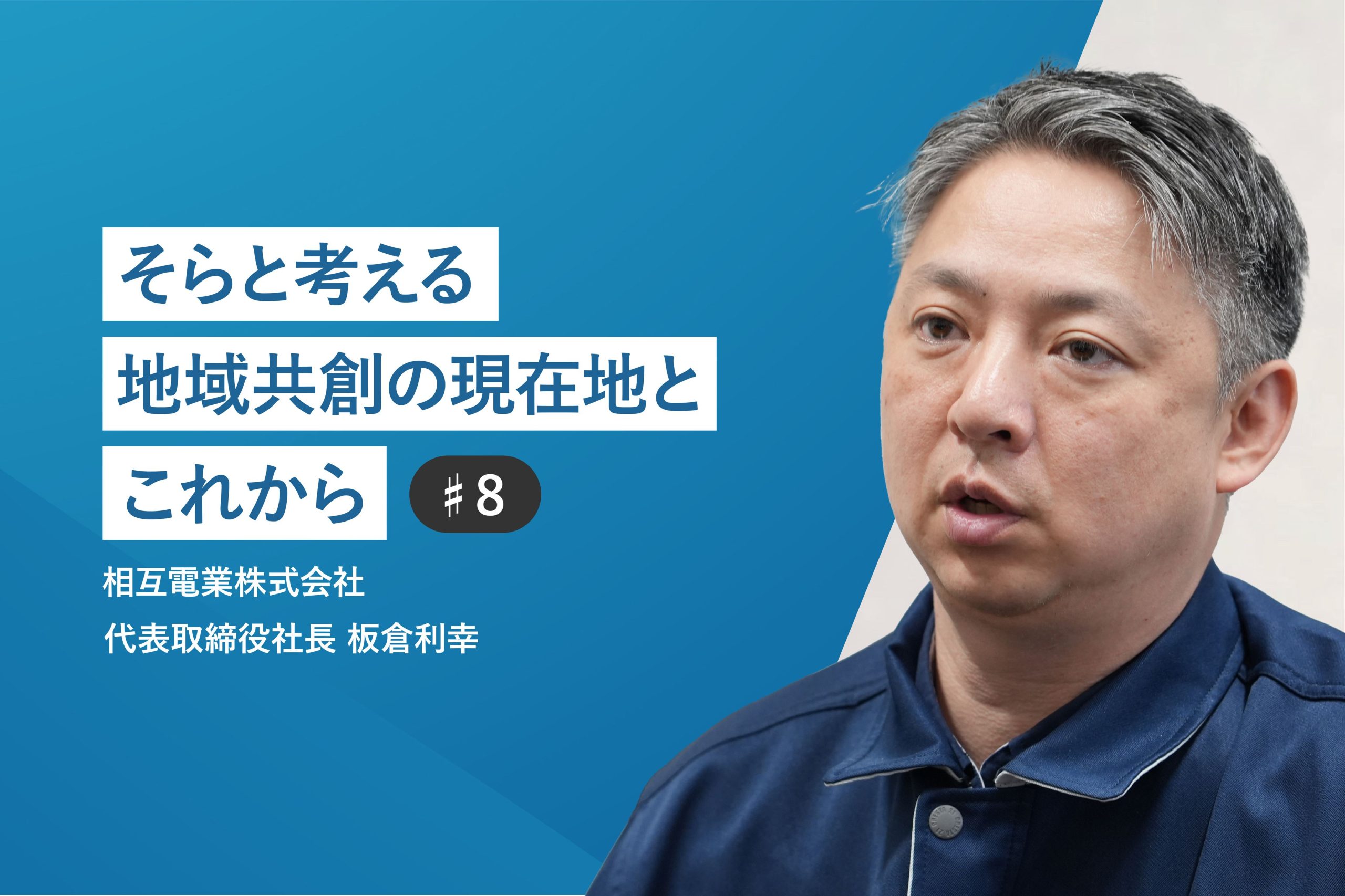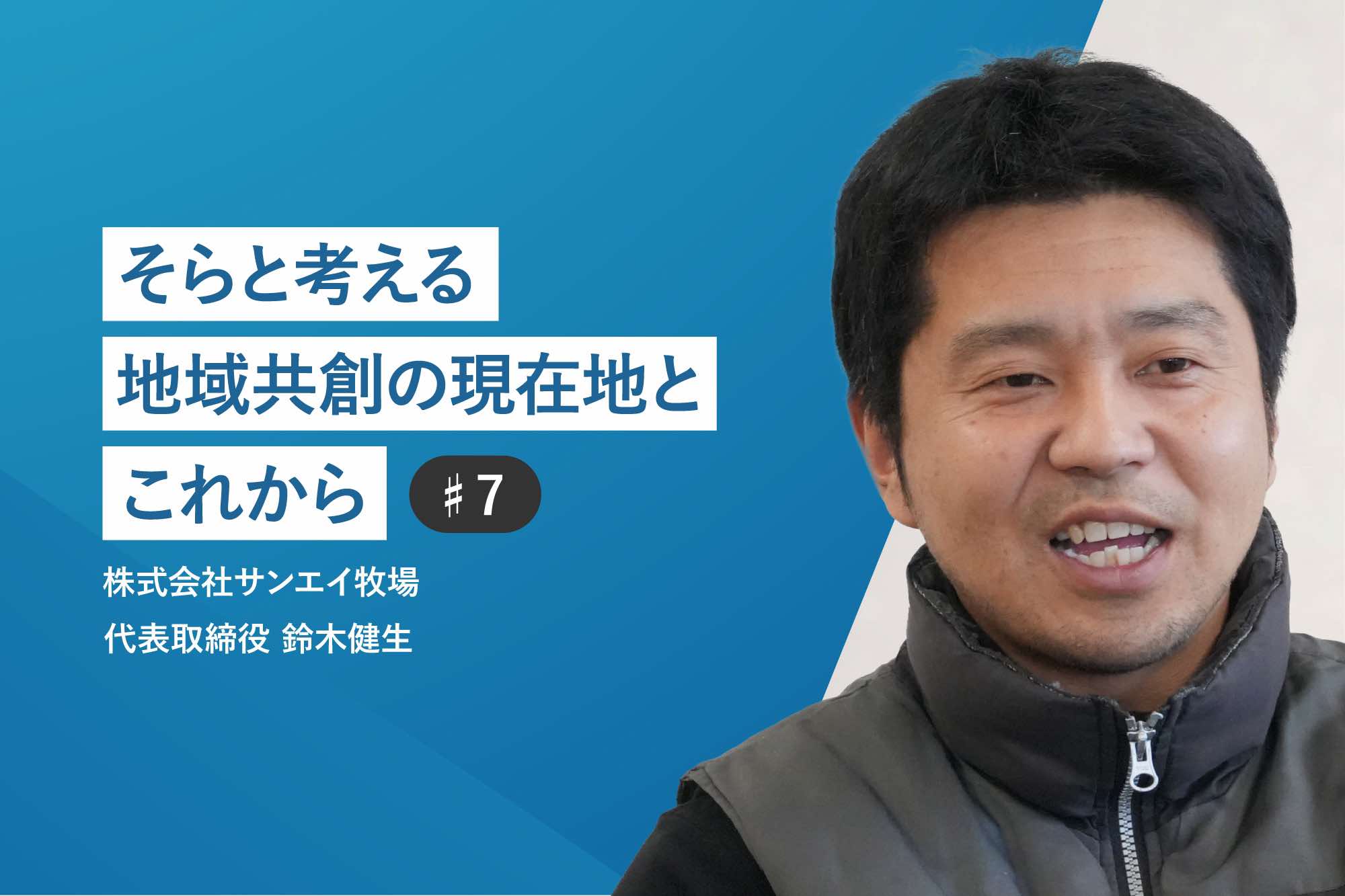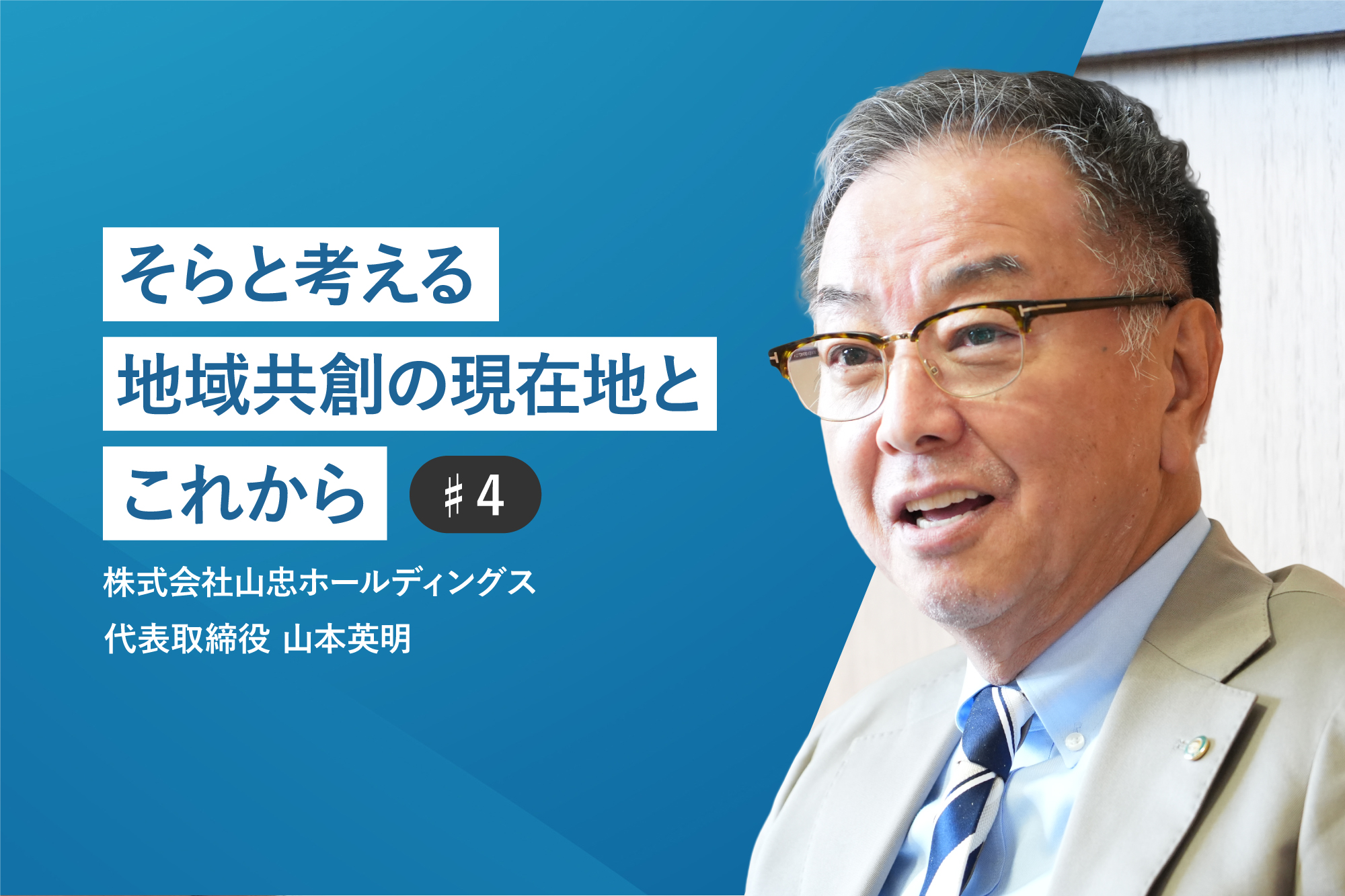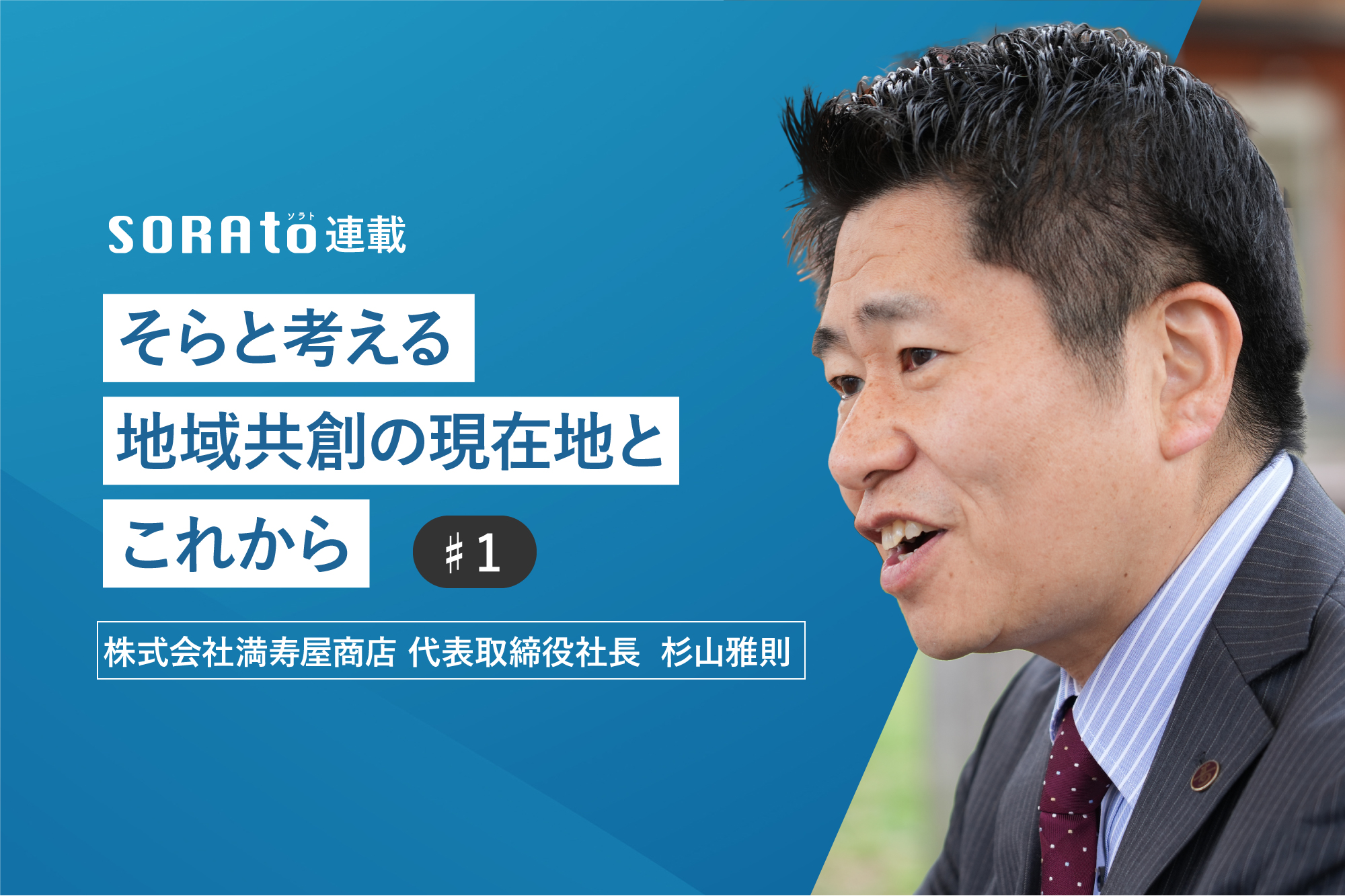第十一回目のフロントランナーは、帯広を拠点にホテル・不動産・福祉・再生可能エネルギーなど多角的に事業展開する株式会社アルムシステムの取締役次長・清信功之介(きよのぶこうのすけ)氏(32)。創業者である父のもと「地域の困りごとをビジネスに落とし込む」哲学で成長を続ける同社は、十勝内外で新施設を次々と立ち上げ、グループ約600名規模へと拡大しています。Uターン後、現場と経営の両輪に携わる清信さんに、幼少期からの原体験、創業者の意思決定、事業を通じた地域共創のかたち、そして十勝への想いを伺いました。
(取材:株式会社そら 三浦 豪・秦 翔悟/記事・写真:スマヒロ編集部)
PROFILE
1993年生まれ。帯広市出身。帯広工業高校電気科を経て北見工業大学・情報電気エレクトロニクス系卒。道外メーカーの営業として東京で1年、九州で5年勤務したのち、2022年にUターンし、アルムシステムへ入社。現在は取締役次長として不動産・ホテル・福祉・エネルギー等の横断案件や新規拠点開発、採用・人材定着施策に携わる。趣味はゴルフとテニス。
※アルムシステムは1988年(昭和63年)創業。前身の清信物産から不動産賃貸・学生下宿を皮切りに、介護(就労継続支援:十勝あすなろ会/北海道あすなろ会)、再エネ(太陽光・バイオガス)、ランドリー、畜産、ホテル「アルムもみの木 帯広東」「ARM双葉」(福島)、「さくらの里双葉」(宿泊・温浴・飲食複合)などを展開。
「普通」に育ち、外で働き、戻って気づいたこと


まず、幼少期の清信さんご自身について。
4人兄弟の末っ子で、いわゆる甘えん坊タイプ(笑)。テニスにのめり込み、小中高大と部活中心の生活でした。家業は身近にありましたが、子ども時代の印象は“学生下宿の家”。やがて介護事業が増え、地域の高齢化に寄り添う会社になっていった、と外から眺めていました。
「継承プレッシャー」は?
長男が7歳上で、早くから経営に関与していたので、私にはプレッシャーはほぼなし。30~40代でいつか戻るかな、くらいの温度感でした。新卒では東京→九州と製造業の営業を経験して、28歳で帰郷。内情を知らずに戻ったら、会社のスケールが想像以上で驚きました。
創業者の意思決定と「地域の困りごと」起点の多角化

アルムシステムの事業は多岐にわたります。意思決定の軸は?
父(創業者)はJC出身で地域ネットワークが広く、「困りごとを解く事業」を次々に形にしてきました。不動産・学生下宿から始まり、介護、ランドリー、再エネ(太陽光・バイオガス)、畜産(清信畜産牧場)、そしてホテル。駅前ホテルの新設や福島・双葉の複合施設など、大きな投資も基本は“地域ニーズ起点”。地域の声に耳を傾け、町との連携を深めていきながら事業を進めています。反対や頓挫もありましたが、大半は成果に繋がり今の事業基盤があります。

再エネは早い時期から?
15年前に売電単価が高い段階から太陽光に踏み出し、屋根設置で断熱性向上など副次効果も得ながら事業化。広尾ではバイオガス発電にも挑戦し、畜産と循環させています。「一歩早く」は父の信条で、今の下地はそこにあります。
Uターン直後は“現場漬け”─電話予約9割のホテルで学んだこと


帯広に戻って最初はホテル現場だったとか。
芽室のホテルに3か月“見習い”で入りました。驚いたのは予約の9割が電話。OTA(予約サイト)手数料を抑え、地域の常連や工事関係の長期滞在に強いモデルです。電話が鳴りっぱなしのカウンター業務で「直販の強さ」を体感し、その後の販路戦略の基礎になりました。
福島の施設にも関与?
はい。被災地の復興需要や工事従事者の滞在を支える拠点づくりで、客室・食・温浴を束ねる運営オペレーションに携わりました。帯広・芽室での知見が、双葉の「ARM双葉」「さくらの里双葉」にも活きています。
分散・多拠点・少数本社─“速い会社”をどう回すか

規模がどんどん拡大されていますね
本社は20数名ほど。対してグループ従業員は約600名規模(M&A予定含む)。現場裁量が大きく、意思決定は速い。社長が方針を示し、役員会で確認して即実行するから、出店や増築のスピードがとにかく早い。一方、サービス業ゆえ人の出入りも激しく、採用・定着・育成の仕組み化は急務です。

人材の受け皿としての「就労支援」も?
障がい者就労の現場とホテルをつなぎ、清掃・ランドリー等で活躍の場を広げています。社長は“入れないとダメだよ”と一貫して言う。地域の人が働ける場所を増やすのは、企業の責務だと考えています。
ホテル戦略は“観光地以外”にもある─需要の読みと現地主義

直近の開発・出店の考え方は?
直近で石狩市の福祉事業を営んでいる会社をM&Aが決まりました。今後はオホーツクエリアでの事業の拡大も進めていく予定です。また帯広駅前、恵庭、美幌ではホテルや飲食を展開・計画中。美幌は「第3館」まで見据え、残地での増築も検討しています。観光一辺倒ではなく、工場・研究所・メンテナンス拠点など“定期的に人が動く”町の需給を丁寧に読む。目で見て歩き、行政とも話し、必要ならグループホームも整備する。M&Aも選択肢。基本は「現地の困りごと」から逆算です。
不動産×福祉×再エネ×畜産─循環で地域を強くする


事業間のシナジーは?
宿泊は雇用と交流人口を生み、ランドリーは地域の家事負担を軽減。畜産は地場の食に寄与し、バイオガスで循環を作る。太陽光は電力の地産地消に一役買い、就労支援は地域の人々に活躍の場を広げる。点ではなく面で地域に関わるほど、事業は持続性を増します。
十勝の強みは「手の届く良質」─外で働き、戻って気づいた価値

北海道外で働いた目線から、十勝の価値は?
東京や九州は外食の選択肢が豊富ですが、良質なものは「高い」。十勝は6,000円のコースでも驚くほど満足度が高い。食の安心・安全に対する信頼が違うんです。加えて空が広く、移動がラク。外を知って戻ると、暮らしの“手の届く良質さ”がはっきり見えてきます。

外との行き来も重視していますね。
福島の施設で帯広の豚丼を出したり、その逆に福島の食材を帯広で使ったり。外部交流は人口減少時代の生命線です。ともに生き、ともに栄える「共存共栄」の精神を大切にしていけば十勝はもっと強くなれます。
「周りが幸せでなければ自分たちも幸せになれない」─社是が導く地域共創

企業理念について。
社訓は端的に“周りが幸せでなければ自分たちも幸せになれない”。スポンサーシップひとつ取っても、“払って終わり”ではなく成果が見える設計を求めます。企業と受け手がWin-Winになれば、地域の潤いは必ず増える。私たち自身も、品質・サービスで確かな価値を返すことが前提です。
これからの10年─「右肩上がりで波を描く」成長と、人が戻れる導線


今後の展望を。
私は性格的に“過度な博打”はしません。ただし何も打たないわけでもない。「右肩上がりで小さな波を打つ」成長が理想です。ホテルは恵庭・美幌の拡張、石狩・釧路圏も需要に応じて。グループホームは行政ニーズがあれば設置。不動産は“安心して住める”インフラを着実に。道外は福島の復興支援を軸に、必要な拠点を増やす。採用は最重要テーマ。働き方や育成をアップデートし、Uターン・Iターンが選びやすい会社にする。“出てよし、戻ってよし”の導線を地域と一緒につくります。
十勝への想い─「賑わい」をつくるのは、暮らしを支える地場企業
最後に、十勝をもっと良くするために必要なことは?
サービス業の立場から言えば、十勝全体が賑わってくれないとホテルも不動産も伸びません。地場企業が“暮らしの基本”を支え、外から人とお金が循環する仕組みを増やすこと。若い人は一度出て、視野を広げてから戻ってくればいい。戻りたくなる受け皿を、私たちが用意する――それがアルムシステムの役割だと思っています。
(取材:株式会社そら 三浦豪・秦翔悟/記事・写真:スマヒロ編集部)
PROFILE
株式会社dandan 代表取締役 | PwCの戦略コンサルティングチームStrategy&、ベンチャーキャピタルの Reapraグループを経て、2021年に株式会社dandanを創業。人や組織は「だんだん」変容するというコンセプトで、企業研修や経営支援、コンサルティングを行っている。2023年に帯広市に移住したことをきっかけに、SORAtoインタビュー企画のディレクターとしても活動している。
PROFILE
群馬県高崎市出身。1996年生まれ。東京農業大学第二高等学校(群馬県高崎市)、成城大学卒業。その後フィリピン語学留学。台湾の大学院に進学。経営学修士を取得後の2022年に三井住友ファイナンス&リース入社。2025年2月、株式会社そらにジョイン。