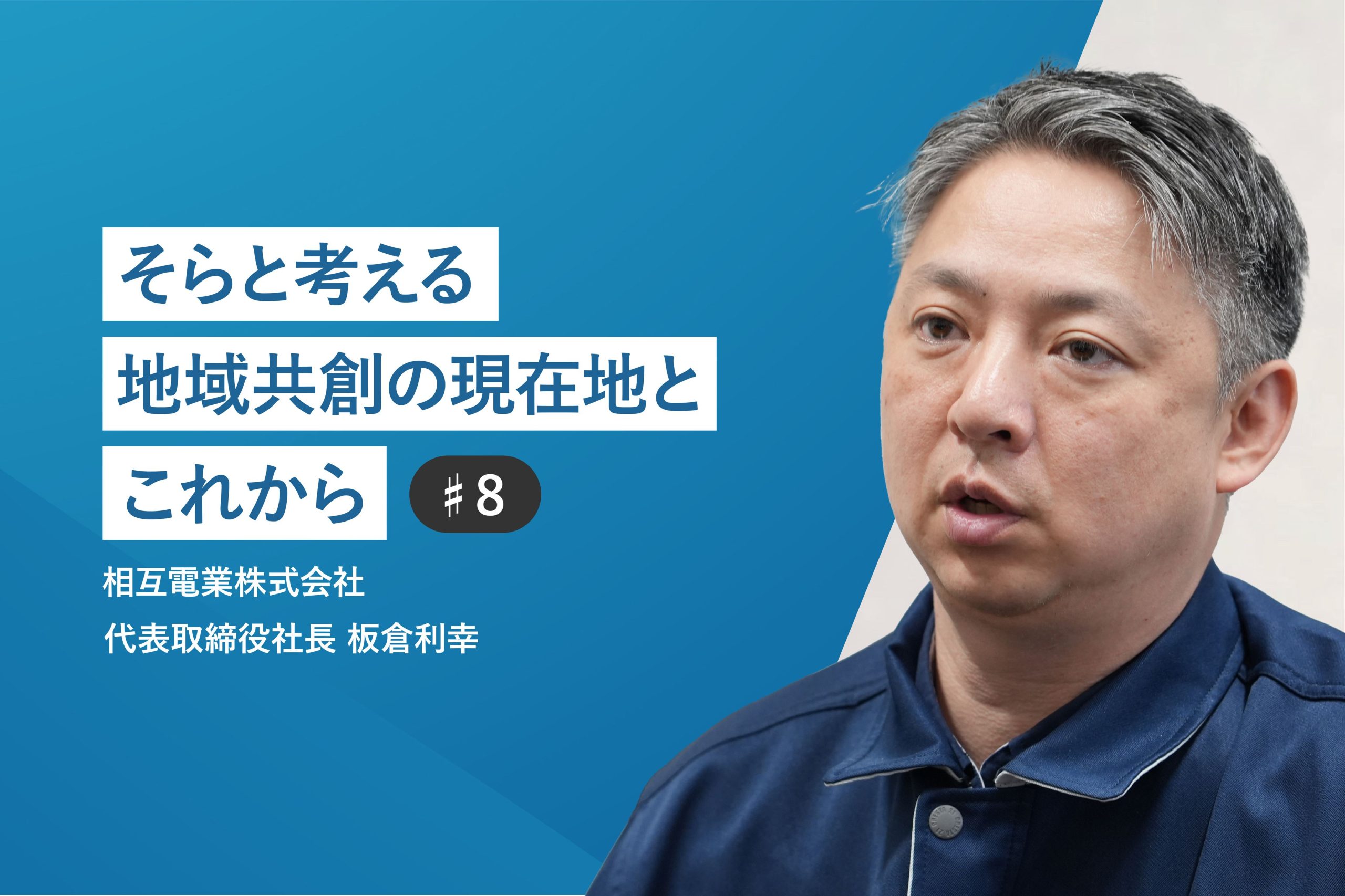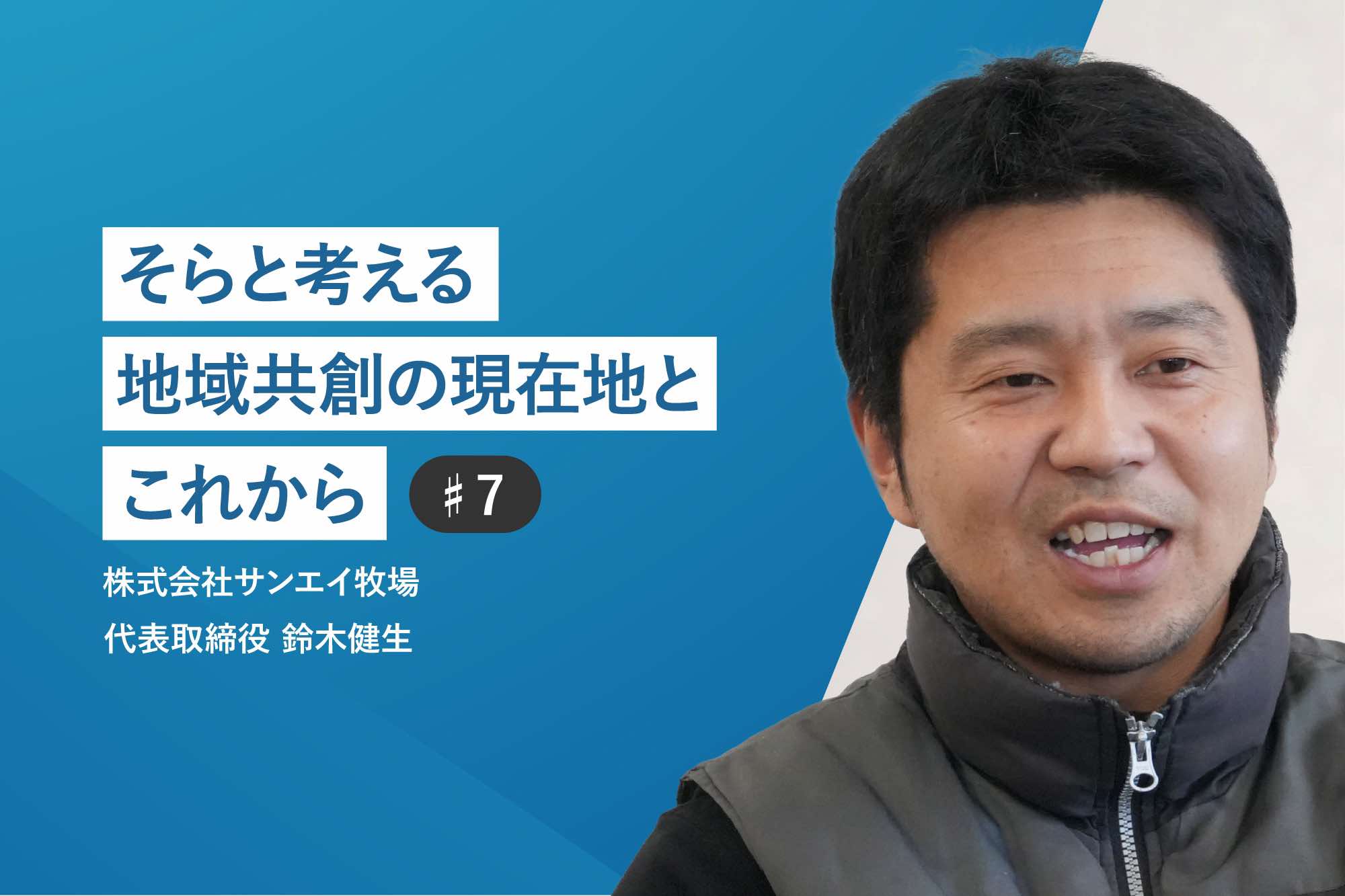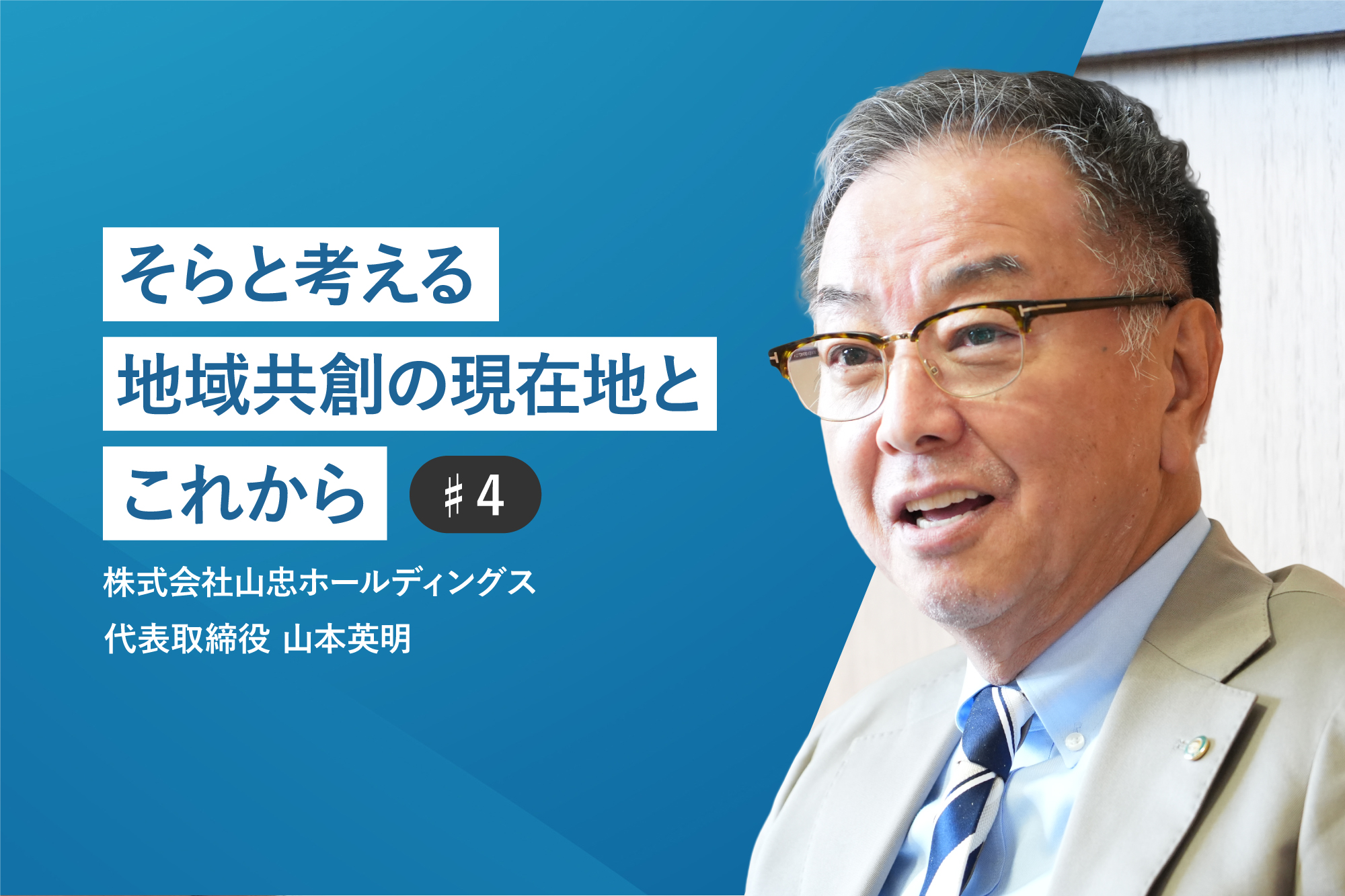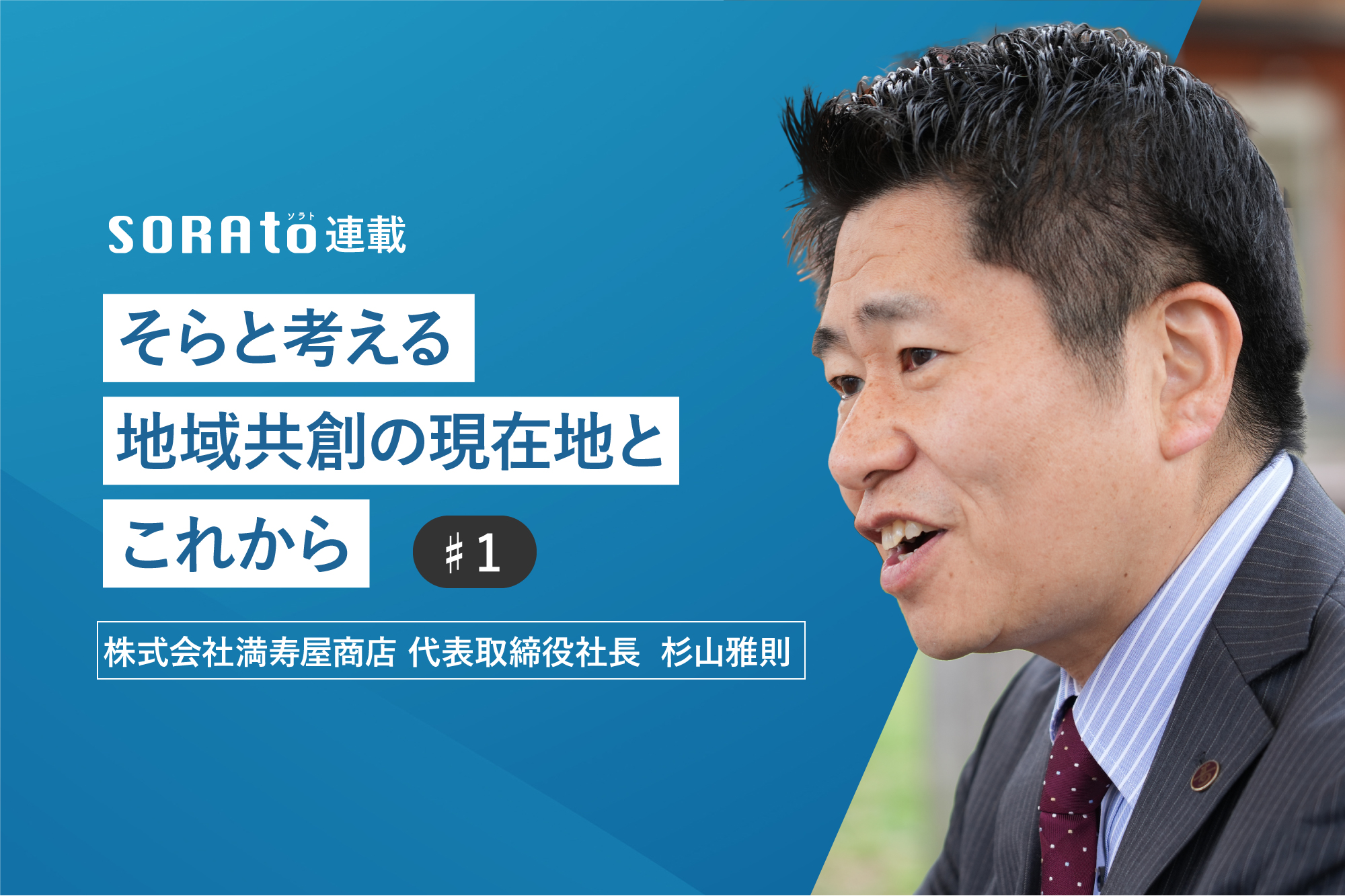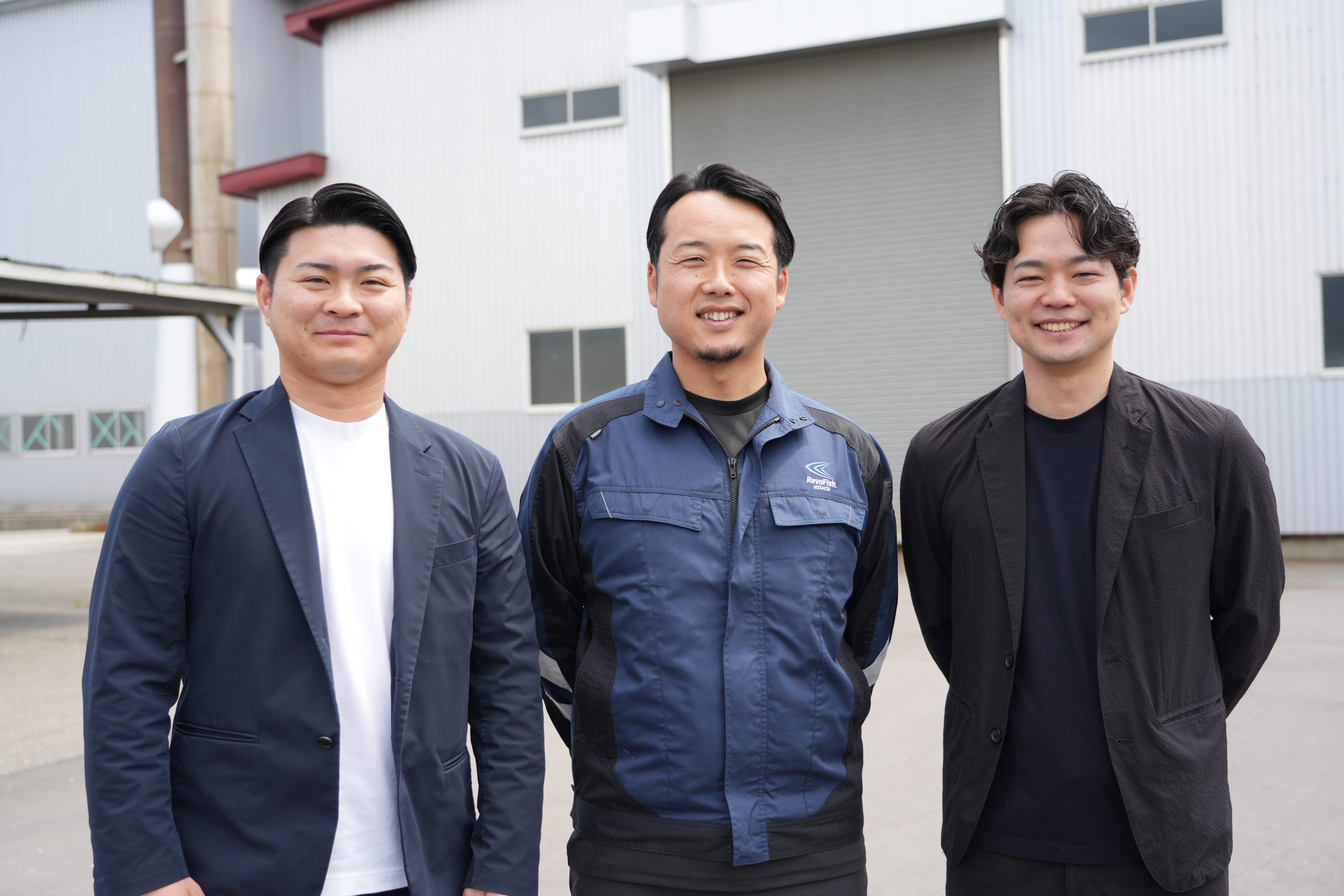
第九回目のフロントランナーは、広尾町で創業70年を迎える水産加工会社・池下産業株式会社の三代目社長、池下藤一郎氏(43)。天然魚の漁獲減による水産不況、異業種への多角化、そして29歳での社長就任――激動の中で彼が掲げたのは、「海の一次資源を再定義し、農業・観光と結びつける“海と山の循環モデル”」でした。幼少期を彩ったサッカー漬けの日々、海外で体感したプロの厳しさ、家業を変革する覚悟、そしてサーフカルチャーを生かした地域戦略まで──三浦豪・加藤直樹両氏が伺いました。(取材:株式会社そら 三浦豪/加藤直樹 記事・写真:スマヒロ編集部)
PROFLE
1982年生まれ。北海道広尾町出身。祖父が創業、父が二代目(現会長)を務める池下産業の三代目。広尾小→広尾中→帯広北高でサッカーに没頭し、帝京大学へ入学。ブラジル(高校時代)やドイツ(小学時代)の短期留学でプロの世界を体感。2005年入社、06年常務、11年10月に29歳で代表取締役社長就任。魚粉・魚油の高付加価値化、液肥輸出、社員寮を兼ねたカフェ「Bay Lounge」など新規事業を次々と展開。従業員約45名。趣味はサッカーとサーフィン。「海と山をつなぎ、広尾を世界の“サーフ&フィッシュ・タウン”へ」がビジョン。
“広尾サッカー少年”が抱いた三代目の宿命

まずご出身と幼少期の環境からお聞かせください。

生まれも育ちも広尾町です。祖父が初代で父が二代目、私は三代目です。幼稚園から中学まで広尾、高校は帯広北高に進学し、小学から始めたサッカーに没頭しました。家業は常に頭の片隅にありましたが、当時は“プロサッカー選手になる”ことしか考えていませんでした。

高校時代にはドイツ・バイエルン、大学時代にはブラジルにも。

ドイツ・バイエルンは、今でこそ、誰もが知る世界的なチームでした。ただ、当時は小学生でしたし、それほど意識せずに合宿に参加していたと思います。とにかく大好きなサッカーを本場ヨーロッパでできる喜びが強かったんです。一方、高校時代に参加したブラジルのサッカー短期留学は全く異なりました。同室の仲間が翌朝突然クビを言い渡され国へ帰る――そんなプロの残酷さとハングリーさを目の当たりにしました。技術より価値観が揺さぶられ、「食べていく厳しさ」を痛感しましたよ。
魚が獲れない──家業を揺るがせた“水産ゼロ年代”


大学卒業後、家業へ戻る決断を下したきっかけは?

2000年代前半は天然魚の漁獲量が激減し、水産加工だけでは立ち行かない。父は広尾・中札内村・帯広市でパチンコ店や大型ゲームセンターを他店舗運営して凌いでいましたが、そこも大手参入で苦戦。大学に行けたのは奇跡的と言えるほど家計的にも厳しい時期だったと思います。それでもサッカーを続けさせてくれた親への感謝が強まり、「恩返しをするなら今しかない」と帰郷し、現場に入りました。
29歳のバトンパス──父子“パートナー経営”の幕開け


29歳で社長就任。当時の心境は?

父自身も29歳で急遽バトンを受けた経験があり、「元気なうちに責任を渡す」主義だったんです。親子関係は良好で、会長と社長が毎朝カフェに集まり1〜2時間“公開ディスカッション”するのが日課。親子であり経営パートナー、そして1番の相談相手で、衝突よりも共創の時間が圧倒的に長い。これは若い経営者の私にとって大きなアドバンテージでしたね。
魚粉・魚油を再定義せよ──縮小市場から薬品・液肥へ


事業転換の軸は魚粉・魚油の高付加価値化でしたね。

従来マーケットは養殖飼料向けと食用油脂(マーガリン等)中心。しかし米国のトランス脂肪酸規制で食用需要が激減し、価格は停滞。「一次原料のままでは縮む一方だ」と考え、薬品用途や海外の液肥市場へ販売網を構築しました。結果、売上は大幅増。単価が上がれば社員の待遇改善に直結します。
“海の副産物”で農産物を甘く──海と山をつなぐ循環モデル


液肥ビジネスが十勝らしい連携を生んでいます。

魚油を搾る過程で出るタンパク質液は従来産廃扱いでした。これを糖度アップ用の有機液肥として商品化し、台湾のパイナップル、中国雲南のイチゴ、そして足寄農協のブランド苺「赤と白」に供給。既存ルートでは10倍の価格で回っていた原料を、私たちが直接提供することで農家のコストを1/10に抑え、付加価値を高めています。海と山が利害で対立するのではなく、循環で結び付く――そんなモデルを十勝全域に広げたいですね。
働き方も刷新──「こんなに休んだのは初めて」の工場へ


組織改革にも大胆に手を入れました。

就任当初、工場は24時間ぶっ通し、繁忙期は誰も家に帰れない。“社長も床で仮眠”が当たり前でしたが、交代制導入と設備更新で土日休みを確保し、給与テーブルも是正。勤続30年超の社員が「休める工場は初めて」と驚くほどです。現在従業員は約50名、7割が広尾出身。事業柄、人数をむやみに増やすより世代交代を計画的に進め、人が辞めない環境を整える方が大切だと考えています。
サーフタウン構想と“タコス革命”──観光の潜在力を解放せよ


趣味のサーフィンが地域戦略に直結しているとか。

工場から車で5分の海は北海道屈指のブレイクポイント。なのにサーファーは閉鎖的でPRしきれていない。僕は外の刺激こそイノベーションを呼ぶと信じています。そこで社員寮を兼ねた「Bay Lounge」を開設し、サーファーや旅人のハブにしました。次は“本物のタコス”とクラフトビールを出すビーチフロント店舗を作ってみたいですね。ちょうど、先日、原宿で出会ったメキシコ人シェフのタコスに衝撃を受け、「これを広尾に持ち込めば第二の宮崎、いや“北のニセコ”になれる」と確信しました。本当にやるかは未来の話ですが……。
十勝への想い──フロンティア精神が育む“挑戦の土壌”


最後に、池下さんご自身が感じる「十勝の魅力」と、広尾・十勝をどんな地域にしていきたいかを聞かせてください。

学生時代に東京へ出て、ブラジルやドイツで本場のサッカーを経験しましたが、これまで、不思議と「十勝は不便だ」と感じたことはありませんでした。空港も近く、海も山もある。何より人が温かい。外へ出て初めて、自然と食の豊かさ、そして“やってみれば何とかなる”フロンティア精神が、この土地の空気に溶け込んでいると実感しました。

そのフロンティア精神は、現在の事業やプロジェクトにも通じていますか?

ええ。水産不況からの多角化、魚粉・魚油の高付加価値化、サーフカルチャーを核にした観光──全部「やるなら大胆に」という十勝気質です。海と山を循環させるモデルも、十勝の農業と水産がそばにあるからこそ形になる。資源を守りつつ稼ぐ“海のSDGs”を実装できる地域は、世界を見渡してもそう多くありません。

地域の若い世代に期待することは?

十勝は、挑戦者にとって最高の実験場だと思います。一次産業も観光もポテンシャルがまだまだ眠っている。失敗しても大地が受け止めてくれる安心感があるので、まずは外へ出て、視野を広げて、その経験を十勝に持ち帰ってほしい。私たちもサーファーやクリエイターが長期滞在できる拠点づくりを進めています。外と交わることで、地域は必ず進化しますから。
(取材:株式会社そら 三浦豪・加藤直樹/記事・写真:スマヒロ編集部)
PROFILE
群馬県前橋市出身。武蔵大学を卒業後、野村證券入社。最初の配属地、とかち帯広営業所でそら代表の米田健史と出会う。その後、大阪の支店で2年勤務。2024年2月、株式会社そらにジョイン。現在は社長室長として社長をサポートする。
PROFILE
株式会社dandan 代表取締役 | PwCの戦略コンサルティングチームStrategy&、ベンチャーキャピタルの Reapraグループを経て、2021年に株式会社dandanを創業。人や組織は「だんだん」変容するというコンセプトで、企業研修や経営支援、コンサルティングを行っている。2023年に帯広市に移住したことをきっかけに、SORAtoインタビュー企画のディレクターとしても活動している。

今回の主役は、北海道・十勝に移住した三浦豪さん。米国シアトルのワシントン大学を卒業し、世界最大級のプロフェッショナルサービスファーム「プライスウォーターハウスクーパース(PwC)」の戦略コンサルティング...